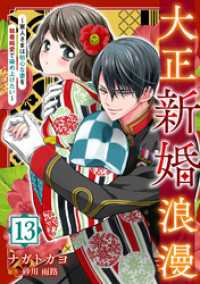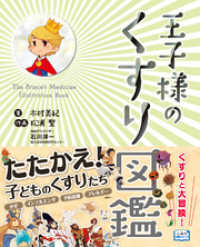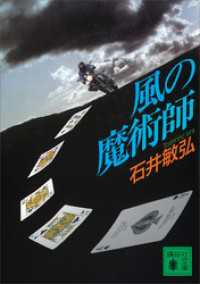出版社内容情報
【解説】
ヨーロッパで農耕が始まった紀元前3000年ごろから紀元前2000年ごろまでの間、フランス・ブルターニュ地方で、延々4キロにわたり、高さが最大6メートルにもなる巨石が並べられた。いったいこれは何か。
新石器時代には北アフリカから北欧にかけてよく似た巨石崇拝の文化が生まれたが、本書では古代の天文施設として有名なストーンヘンジのみならず、さまざまな地方の遺跡を取り上げ、謎めいた全貌を明らかにする。
内容説明
巨石建造物は大昔からさまざまな伝説で彩られてきた。とある地域の巨石建造物は荒地の真ん中で、踊る少女たちの行列がやってくると、身を起こして少女たちを通してやったという。
目次
第1章 伝説の石
第2章 古代研究家と学者たち
第3章 巨石建造物の3000年
第4章 死者と神々の宮殿
第5章 天と地の間で
著者等紹介
モエン,ジャン・ピエール[Mohen,JeanPierre]
フランス博物館研究所の所長。アンドレ・ルロワ=グーランの指導の下で、先史学の国家博士を取得。グラン・パレで“ケルト王の宝物展”(1987年)など数々の展覧会を開いてきた。主な著作に「巨石建造物の世界」「先史時代の冶金」などがある。’92年まで、サン=ジェルマン=アン=レー国立先史学博物館館長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。