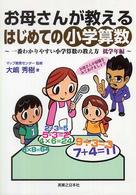出版社内容情報
【解説】
阿闍世コンプレックスとは、精神科医古澤平作が、フロイトの提唱したエディプスコンプレックスに刺激されて考えだした、きわめて日本的な母子間の心性のことである。本書は、まずその歴史的背景から、仏典の読み方、日本版阿闍世王物語の生まれる背景、さらには虐待など、さまざまな現代の母子間の臨床事例に見られる阿闍世の問題まで、ほぼ全域を網羅し、最高の執筆陣によって書き上げれらた阿闍世コンプレックス研究の決定版である。
【まえがきより】
小此木啓吾
本書『阿閣世コンプレックス』の刊行は私にとって大変うれしいことだ。一九三二年、古澤平作先生が阿闍世コンプレックスをウィーンのフロイトに提起してから、ほぽ七〇年を経て、ようやく阿闍世コンプレックスをタイトルにした単行本が刊行されるからだ。
私がこのテーマにかかわるようになってからでもすでに五〇年近くたっている。ようやく本書の刊行が可能になったのは、私たちのそれなりの学問的準備と、その刊行を可能にする環境が整ったためである。とりわけ本書は、私のこれまでの研究の蓄積のみならず、私と同じ世代で古澤先生から直接ご指導を受けた、西園さんをはじめとする第二世代、そして、私から間接的に古澤一阿闍世コンプレックスについて聞いたり読んだりしている、深津千賀子、滝口俊子、櫻井昭彦、高野晶らのいわば第三世代の人々、この二つの世代の協力によって可能になった。そして古澤は最初から西洋のフロイトとちがった仏教的な宗教的心性を主張している。この課題について滝口俊子さん、横山博先生の参加を得て、阿闍世論のより開かれた交流の道をひらくことができた。とりわけ、こうした編集の作業には、共同の編集者である北山修さんの多大なご尽力がある。これらの方々の協力があってはじめて、本書は刊行される。
私にとって阿闍世コンプレックスは、実のところ、とてもアンビバレントな対象であった。古澤先生の残された文献は短い二つの論文だけである。精神分析理論としての着想も直観的なもので、それをどんなふうに整理・推敲して一つの精神分析理論として位置づけるかについてはかなりの苦労があった。それだけに、機が熟するまで、そのつどまとめを発表しても、積極的に仕上げようという気持ちになかなかなれなかったというのがホンネである。
たとえば、阿闍世コンプレックスという以上、本来なら阿闍世の精神内界の葛藤や幻想、またその投影として理論づけるのが筋である。仏典の中にはこの路線を支持するようなものもあるらしい。つまり、阿闍世に、親の子捨て、子殺しのような妄想を抱かせたのは、堤婆達多の事実無根の虚偽の中傷だった。「父母は何も悪いことはなかったのに・・・だからその罰で堤婆達多は地獄に落ちた」という極端な話である。たしかにこの路線なら、子どもの側の原幻想としてとらえるフロイトのエディプス・コンプレックス論との一軍性も得られる。ガンザレイン先生の罪悪感の防衛磯制論も、クライン派らしいこの観点に準拠しての妥当な論議だと思う。
しかし、どうもこれだけでは、古澤の、そして私の論議には不足である。母、韋堤希(いだいけ)の側の葛藤は客観的事実として存在するという視点を古澤も語っている。では、韋堤希の葛藤と阿闍世コンプレックスはどういうかかわりになるのか。親の虐待と心的外傷説で割り切れれば話は簡単だが・・・。そうこうするうちに、エディプス物語の前半、つまり父母ライオスとイヨカスタの子捨て、子殺しの葛藤がテーマになり、父親における子殺し衝動、その葛藤をライオス・コンプレックスと呼ぶような動向も生まれた。このひそみにならうと、阿闍世コンプレックスとともに韋堤希コンプレックスをもう一つ新たに提起するほうが筋が通るという考えもある。何しろコンプレックスという言葉は、一人の人の心の中に抱かれる観念・情動複合体が本来の定義だからだ。
しかし、この二つのどちらの道でもない、第三の道を私は臨床的にも見出した。その一つは、母子並行・同席治療などの臨床におけるレボビッシ先生の、母親の葛藤と幻想の赤ん坊の世代間伝達の研究であった。フェダーさんやラファエル・レフさんとの出会いも、この私の歩みに大きな支えになった。本書にこのお二人の友情を記念する論文が貞安元君の名訳によって掲載できて、とてもありがたく思っている。もう一つは、本来私が志向していた、そして、おそらくは古澤自身が本当は理論化を望んでいた、韋堤希と阿闍世の二者心理学的な相互関係論を普遍的なものとして語る現代精神分析の治療関係論の展開が生まれたことである。
特に、この二つの精神分析の流れを私なりに理論的かつ臨床的に消化することで、ようやく私は阿闍世コンプレックス論を一つの精神分析理論として形づくることができたように思う。そして、このことが本書刊行の学問的な条件の成立であった。このあたりの私の学問的な苦心は、妙木浩之さんが、本書の論文「記憶と物語」でとても適切に読み取っている。しかも、そこで古澤先生の苦労された治療対象である境界例の臨床に目を向けている。ちなみに、古澤先生の脳梗塞の発症は、境界例の方の自由連想中にお倒れになったときであった。
さらにもう一つ、阿闍世コンプレックス論を積極的に提起するための私なりの苦労があった。そもそも阿闍世の物語は仏典の中に数多くある。しかも、そのほとんどすべてが父王と息子阿闍世の物語を主題とみなし、母との葛藤を二次的なものに位置づけている事実である。それだけに古澤の阿闍世コンプレックス論については、仏教界から何人もの学者、識者からの半ば非難に近い批判が寄せられた。
この批判に対してどんなふうに対応し得るかもまた、二代目の私の悩みであった。この点については、精神分析理論で輪廻=世代間伝達の形での母韋提希と阿闍世の関係性を明確にする臨床経験が豊かになり、さらに、観無量寿経を古澤-小此木版の主な原典とする方向性を確立することで、かなり大きな展開がこの領域で可能になったと考えている。
そして、私個人の気持ちとしては、これで古澤版阿闍世論にもはやとらわれることなく、もっと気楽に、仏典のさまざまな阿闍世物語を全体的な視野に入れて阿闍世コンプレックスを論じる自由が私たちに与えられると考えている。すでにその一つの出発が、今回のIPAニース大会での、二者関係と三者関係の間に阿闍世コンプレックス論を位置づけるという動向である。そしてこの動向はこれからの阿闍世論をさらに発展させる一つの課題になると思う。
いずれにせよ、本書の刊行は、古澤から三世代にわたる七〇年間の阿闍世コンプレックス論の一つの集大成である。この歴史的な意義を持つ刊行にちなんで、古澤平作先生のご子息古澤賴雄先生から、古澤平作における阿闍世コンプレックスの起源を明らかにするというべき貴重なまえがきをいただいた。佐藤紀子、木田恵子さんらの第二世代の方々の論文とともに、本書はこの意味で、阿闍世コンプレックス論のみならず、日本の精神分析の父というべき古澤平作研究のワンステップになると思う。
また、現代の母性と阿闍世コンプレックスについて、わが国における母性研究の第一人者である大日向雅美先生と私たちとの鼎談を本書に掲載することができた。現代社会に生きる女性たちが、葦提希と阿闍世の葛藤をそれぞれの身近な課題として本書をお読みいただければ幸いである。
【目次】
まえがき
父、古澤平作と阿闍世コンプレックス
1 展望
「阿闍世コンプレックス論の展開」
「討論 阿闍世コンプレックス」
2 原点と仏典
「罪悪意識の二種-阿闍世コンプレックス」
「阿闍世王の物語について」
「古澤版阿闍世物語の出典とその再構成過程」
「『罪悪意識の二種』の仏教的背景」
3 阿闍世コンプレックスにおける罪とゆるし
「記憶と物語-『罪悪意識の二種』によせて」
「自発的罪悪感はどんなふうに体験されるか-精神分析と観無量寿経における」
「阿闍世コンプレックスに含まれる種
内容説明
母と子の罪とゆるし、精神分析と仏教の出会い―本書はその日本にオリジナルな臨床と研究の展開である。
目次
1 展望
2 原典と仏典
3 阿闍世コンプレックスにおける罪とゆるし
4 母親が子どもを持つことの葛藤
5 阿闍世物語における母性原理
6 阿闍世コンプレックスと古沢の人間的背景
7 阿闍世と現代の母性について(鼎談)
著者等紹介
小此木啓吾[オコノギケイゴ]
1930年生まれ。慶応義塾大学医学部卒業。東京国際大学大学院臨床心理学研究科教授、慶応義塾大学環境情報学部客員教授。慶応心理臨床セミナー講師。医学博士。精神分析学、精神医学専攻
北山修[キタヤマオサム]
1946年淡路島に生まれる。1972年京都府立医科大学卒業。札幌医科大学内科研修生を経て、ロンドンのモーズレイ病院およびロンドン大学精神医学研究所で研修。帰国後、北山医院院長。現在、九州大学大学院人間環境学研究院・医学研究院教授。精神分析学専攻。国際精神分析協会正会員、日本精神分析学会会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 和書
- 死に方が知りたくて