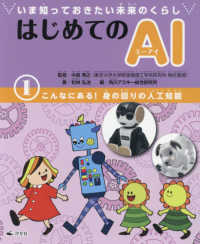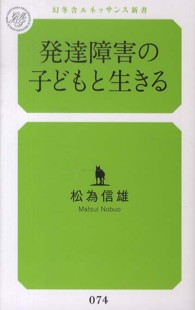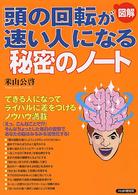出版社内容情報
昆布だしと食材、調味料との組み合わせの方程式、うまみについての考えなど、1冊で「だし」の使い方が分かる本。
昆布だしと食材との組み合わせで、おいしい料理はできる。だしと食材、調味料との組み合わせの方程式、うまみについての考えなど、1冊で「だし」の使い方が分かる本。また、ひとつのだし+食材の組み合わせから、汁物、惣菜、ご飯に展開する方法も紹介。
昆布さえあれば、おいしい料理はできる!
新富町「潤菜どうしん」の料理長、矢長謙三さんの人気料理教室から、日々の食卓に生かせる「だし」の取り方と使い方を教えます。
基本の考え方は「昆布だし+食材のたんぱく質」。
昆布だしと食材との組み合わせで、おいしい料理は作れます。
また、野菜や肉の茹で汁も「だし」として余さず使う方法なども伝授。汁物はもちろん、惣菜、ご飯に展開する方法も紹介します。
昆布だしの取り方、食材や調味料のおいしい組み合わせを、「うまみ」表を使い詳細に解説。
だしをとりなれていない人にも、毎日だしをとっている人にも参考にしていただける1冊です。
はじめに 「じゅうぶん」な味にするために
基本の昆布だし とり方/使い方
「まずはここから」の味噌汁
大豆食品で味の「強さ」を見ましょう
1 昆布だし+魚介
アサリ アサリうどん/アサリとホウレンソウのおひたし/だし巻き/アサリのトマトソーススパゲティ
ホタテ水煮缶 だし巻き玉子
サンマ 炊き込みご飯
鮭 粕汁
鯛 失敗しないお吸い物
イカ ワタも調味料に
アジ アジの干物を使ったおひたし ほか
(コラム)薬味の種類と使い方
2 昆布だし+肉
鶏 冬瓜と手羽元の煮物/鶏肉・キュウリ・ウドの梅肉和え/鶏だし茶漬
豚 新ジャガイモと角煮/シンプルラーメン
牛 しぐれ煮/肉うどん ほか
(コラム)昆布の活用法 鶏ごぼう巻き/佃煮/かりかり揚げ
3 昆布だし+野菜
トウモロコシ すり流し
カボチャ どうしん流ポタージュ
エンドウ豆 うす葛でとじたクリームスープ
季節の野菜 和風ポトフ/旬の小鉢とスープ
白菜漬 豚バラと漬物の中華風スープ
納豆 たたき納豆汁
キノコ サトイモのきのこあんかけ/なめたけ
(コラム)野菜の茹で方、煮込み方
4 昆布だし+乾物
アミエビ ナスの煮びたし/アミエビごはん/アミエビ・豆腐・ネギの味噌汁/桜粉ふき芋/三杯酢
鰹節/干しシイタケ/切り干しダイコン/ソフトニシン/切り麩/ワカメ ほか
(番外編)昆布だしを使わない 茶飯
(コラム)調味料の「うまみ」と「あまみ」
【著者紹介】
1977年岡山県生まれ。山口県岩国の割烹料理店を経て、京都の旅館「八千代」、東京「馳走 卒啄」などで修行をする。08年に和食の店「潤菜どうしん」を開店。定期的に開いている人気の料理教室のほか、雑誌や講演会などを通して、昆布を中心としただしのとり方、日本料理の考え方を広めている。国内の在来品種など野菜にも詳しく、青果流通業者などが受講する「よこはま青果塾」講師も務める。
内容説明
現代の日本料理は、味を「薄める」より「強める」ことに意識が注がれ、過剰な「おいしさ」が溢れているように感じます。しかしそれは、本当に体が求める味でしょうか?この本では、食材に含まれるうまみ=だしと昆布だしを合わせて、体に負担のないおいしさ、過不足のない「十分な味」を作る方法を紹介します。食材の持つうまみの強さや、お椀の中でのうまみのバランスなど、舌の感覚を分析した「うまみ割合表」も紹介。感覚を磨き、日々の味を作るヒントとしてお使いください。
目次
だしの基本
「まずはここから」の味噌汁
昆布だし+魚介
昆布だし+肉
昆布だし+野菜
昆布だし+乾物・保存食
著者等紹介
矢長謙三[ヤナガケンゾウ]
1977年岡山県生まれ。山口県岩国の割烹料理店を経て、京都の旅館「八千代」などで修業をする。08年に和食の店「潤菜どうしん」を開店。国内の在来品種など野菜にも詳しく、青果流通業者が受講する「よこはま青果塾」講師も務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
めしいらず
たんぽぽ
BEAN STARK
彼方
аяка