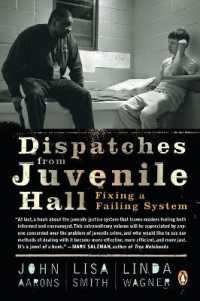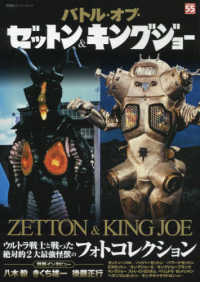出版社内容情報
◇ 解 説 ◇
現代人はたえず社会的圧力の中で生存をつづけ,しばしば自分の意志でない「決定」「選択」を強制されている。本書はその結果生じる「心の不協和」のメカニズムと,その解消のダイナミックスに応えたものである。
◇ 目 次 ◇
1.不協和理論への序説
2.決定の諸結果:理論
3.決定の諸結果:データ
4.強制的承諾の効果:理論
5.強制的承諾の効果:データ
6.情報に対する意図的接触と無意図的接触:理論
7.情報に対する意図的接触と無意図的接触:データ
8.社会的支持の役割:理論
9.社会的支持の役割:影響過程のデータ
10.社会的支持の役割:大衆現象に関するデータ
11.総括および将来への示唆
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イボンヌ
5
昭和40年出版の、学習者向けの学術書でした。一般向けに書かれたものではなく、歯が立ちません。2025/03/02
yakisamako
2
認知的不協和とは認知(意識)に矛盾を抱えることにより不快な状態が存在すること。人はこの不快感を低減するために自分の行動や態度を変更していく。例えば健康に良くないと知りつつも喫煙がやめられない人は「健康に悪くても精神的にはいい」「煙草をやめても人間はいつかは死ぬ」等の態度をとることで合理化をし不協和を低減させることに成功する。もっと簡単に言えばイソップの「狐と葡萄」○○はインチキなのにどうしてあの人たちは頑なに信じ続けるのだろう?そんな疑問も認知的不協和が絡んでいるとわかれば少しは納得できる。面白かった。2021/12/13
新橋九段
2
実験のデータは古いし手続きは入り組んでいるけど、理論のところは興味深い話が多い。結構いろいろな分野に手を伸ばせそうだな。2018/04/09
こずえ
1
認知的不協和とは、それまでその人が信じてきたものと反する事実を知ったときにその矛盾を解消するために、事実を否定したり罵ったりと、ともすると非論理的な行動をとろうとすること。 社会心理学の中の1つ。 そのため心理学だけでなく法学部で扱われることもある
不以
1
用語の定義をはっきり示し平易な言葉遣いで章ごとに要約がある、読みやすい。なるほど確かにそうだ、と何度も感心させられた。(以上の好意的感想は不協和を解消するために書いてしまったのかもしれない)2012/06/02