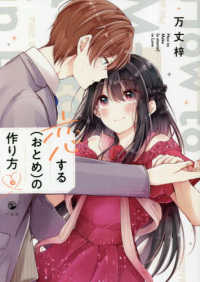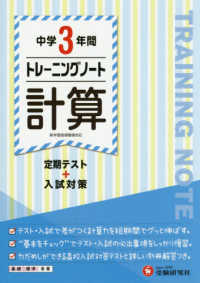内容説明
横山大観、菱田春草らに代表される日本画の表現、「朦朧体」。彼らの画によくみられる輪郭をぼかした描き方は、今では当たり前に受け止められているが、当初は伝統を台無しにするとして多くの非難を浴びた。本書では当時の批評をもとにその言葉の変遷をたどり、彼らが西洋画に対してどう新しい日本画を構築していったかを描く。明治の浪漫主義、大正のモダニズムとむすびつき、さらにはインドの独立運動なども巻き込んでナショナリズムともむすびついた「朦朧体」を手がかりに激動の時代を探る。
目次
第1章 伝統回帰か西洋化か―朦朧体の基盤づくり
第2章 “こころもち”の絵画―朦朧体前夜
第3章 日本美術院の絵画運動―朦朧体の表現とは
第4章 「朦朧体」の出現―明治における「朦朧」のイメージ
第5章 批評者たちとの闘い―「朦朧体」の意味
第6章 画壇への波及と追随者たち―朦朧体の確立
第7章 アジアへの憧憬―インド人画家たちの朦朧体
第8章 西洋へのアピール―朦朧体の思想的背景
第9章 近代日本美術史の成立―朦朧体の評価
著者等紹介
佐藤志乃[サトウシノ]
1968年生。公益財団法人横山大観記念館学芸員、立教大学兼任講師、博士(芸術学)。専門は近代日本美術史。朦朧体をはじめ、明治・大正期の日本美術、近代の日印美術交流に関する論文がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
湿津
1
良著だった。朦朧体について、蔑称であったことも批判を受けた技法であったことも知っていたが、単に「ぼんやりしている」程度の意味を持つものとして捉えていた。西欧化の波に押され、写実至上主義に押され、伝統に雁字搦めになっていた日本画に朦朧体がどのように影響したのか。そして、美術界にどのように受容され変化して言ったのか。やっぱりこの頃の美術界ってドラマチックだ〜!日本画って今でこそ堅苦しいイメージを持たれがちだけど、アツい気持ちを持った人間たちが画壇風穴開けようとしてるさまを見ると胸が熱くなる。素晴らしい!2024/04/27
邪馬台国
0
朦朧体を通して明治期の日本画を読み解く。朦朧とはおぼろげな情緒あるものだと捉えていたが、当時は伝統に反し、不明瞭で妖怪のような扱いを受け批評家達に猛叩きにあっていたというのは驚き。現代は技法的・伝統的観点から袋だたきの非難を浴びる事はないくらい多様化が進んでしまった世の中ね、良くも悪くも…… 当時の情勢から切り離された視点で鑑賞すると、結局は作品の生まれた時代背景など二の次、まずはただ美しいか否かという観点でみてしまうし、いつの時代も“美しさ”は伝統や文脈といった“情報”を蓄え過ぎると判断が濁る。2013/09/02
-
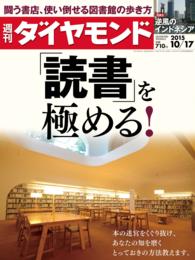
- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 15年10月17日号…