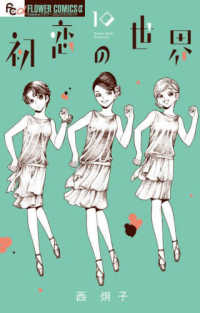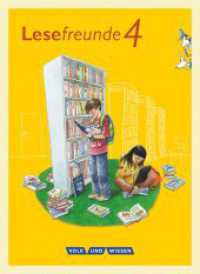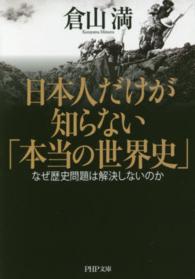出版社内容情報
先鋭化する欧米のニューメディア研究、フィクション論、認知科学など最新の知見を導入し、来るべき「映像の理論」に向けた挑発の書。
内容説明
現在、「映像」はあらゆる場所に溢れ、私たちの生活において不可欠のものとなっている。アナログからデジタル映像への変化、インターネットなど画面を通した双方向コミュニケーション技術の進歩とその爆発的拡大などにより、もはや「映像」はただ眺めるだけのものではなくった。変貌した「映像」が持つ意味と、それが与える衝撃とは何か。北米のニューメディア研究、欧州のイメージの科学をはじめ、情報理論、認知科学、脳科学、分析哲学、映画、ゲーム、メディアアート、フィクション論など、多岐にわたる分野を大胆に横断し、来るべき「映像の理論」を構築する、挑発的な一書。
目次
序章
第1章 画面とは何か(アナログとデジタルの断絶と連続;映し出されたものと映し出されるはずだったもののあいだ)
第2章 映像と身体(見つめる身体と操作する身体;身体イメージの厚みと膨らみ)
第3章 映像とその外部(映し出された物語と語られた物語;遮断する映像と接続する映像)
結語 言葉と映像、その新たなる距離
著者等紹介
北野圭介[キタノケイスケ]
1963年生。ニューヨーク大学大学院映画研究科博士課程中途退学。ニューヨーク大学教員、新潟大学人文学部助教授を経て、立命館大学映像学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あんすこむたん
1
様々な人物の著書を参考にしながら、様々な視点で深く論じていく。内容が濃いので一読で全てを理解することは難しいだろう。「小さなまとめ」あるのである程度理解しやすくはなっている。2018/01/24
mittsko
1
力作!すごい! 通俗的なデジタル/アナログ二分法への批判を梃子に、現代の「映像」的人間をとらえようとする試み ものすごく的を射たねらいだと思う… 普遍化と個別化(歴史化)、論理と「信仰」、それぞれのバランス感覚が心地よい(とくに後者は、方法論的反省のつよさを反映しているんだろうな) 察するに、アメリカ映画学の理論的水準を、批判的に消化して出来上がった論筋であろうかと… こういうのが日本語で読めてしまうのだから、本当にお得だ! すばらしいです☆2011/01/22
ubon-ratchat
1
映像周りの問題系を扱った論者をある程度網羅的に把握するのに好適。映像について何事かを書いてみたい人は必読。しかし、真面目な話、筆者の着地点がよくわからなかった……第三章はもう一度読むべきか。2010/11/05
枯れる蓮
0
2週間掛かった。2016/09/15
へび
0
再読ー2015/08/28