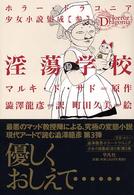内容説明
アヴァンギャルド文学芸術運動がヨーロッパを主要舞台として展開し、それが世界各地域に波及していったのは事実である。しかしその形成過程や内的構造にまで分け入ってみるならば、彼らの作品は、ヨーロッパの外部に由来する表現様式からインスピレーションを受けたことで、その構造自体が生まれ変わってしまったと言ってもいい。
目次
第1部 二〇世紀アヴァンギャルドとプリミティヴ・アート(ピカソと“アヴィニヨンの娘たち”;アポリネールと「太陽首切られて」/ツァラと「黒人詩に関するノート」;ストラヴィンスキーと『春の祭典』―ロシアの場合;シュルレアリスムのヨーロッパ批判―表象の人類学的変容)
第2部 アヴァンギヤルドの思考から世界の生成へ(エメ・セゼール―世界というトポスの身体化;オクタビオ・パス―世界を受肉する詩学;荒川修作―世界のつくり直しとしての「建築する身体」;世界、そして見えない都市へ)
著者等紹介
大平具彦[オオヒラトモヒコ]
1945年生。東京都立大学大学院博士課程中退。北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院教授。表象文化論、国際地域文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
dilettante_k
1
09年著。20世紀初頭に始まったアヴァンギャルド芸術を、ヨーロッパ的思考と彼らが絶えず参照したプリミティヴ・アートとの合力(クレオール)と位置づける。ピカソやアポリネール、ストラヴィンスキー、シュルレアリストがヨーロッパ的思考を内破しようとする一方、セゼールやパス、荒川修作ら周縁の出身者たちが、ヨーロッパ的思考を超克し、トランスナショナルなトポスを創造したと指摘する。概念を次々と等号で結び付け、対立する視点(例えばルービンとクリフォード)も糾合する記述は危ういが、20世紀の構造転換を概観した意欲的著作。2015/04/05