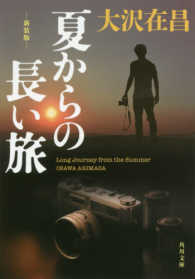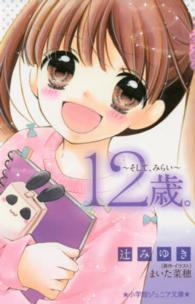- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
原子力発電所、事故の可能性は?選挙は民意か?物事の本質を見抜く「頭のよさ」は「数学的発想」で身につけられる!
目次
第1章 頭がいいとはどういうことか
第2章 能力はどのように育てるか
第3章 「数学的発想」で頭をよくする勉強法
第4章 「数学的発想」を鍛える数学の勉強法
第5章 知的好奇心で学ぶ数学文化
第6章 数学とコンピュータ
第7章 社会で数学はどう役立つか
第8章 「数学的発想」で未来を開く
著者等紹介
小林道正[コバヤシミチマサ]
数学教育協議会委員長。1942年長野県生まれ。京都大学理学部数学科卒業、東京教育大学大学院研究科修士課程修了。1980年から中央大学経済学部の教授を務め、2013年退官。専門は、確率論、数学教育(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まつど@理工
6
栗田哲也『数学に感動する頭をつくる』p260「本格的な道を歩んだ人と、単に数学的リテラシーの教育をされた人との間には今までにはなかった悲惨なほどの「格差」がつく時代がすぐそこにまできている」という点を考慮するとこの本はイマイチである。しかし「数学活用」などの応用が重点化されつつあることもあり、このような本を読んでおく意義はあると再読して思いました。2014/05/01
まつど@理工
6
ちょっといまいちかな。数学を「物事を考える基本ツール」としてみるのなら、計算機導入もアリだと思うけど、数学の深みに近づくためにはできるだけ頭のなかで概算なりができる必要がある。数学は好きな分野から学べるという指摘は僕も大事だと思う。線型代数は中学生でもわかるというのも、「基礎演算」としては納得する。がしかし数の組をnまで拡張していくなかで、数学世界を豊かにするような「線型代数」の面白さは、時間をかけないとわからないと思う。栗田哲也『数学に感動する頭をつくる』の方が純粋に数学を楽しむには適している。2013/09/30
月と星
3
★★★クールな頭と温かい心を持つ,へりくつを見破る目を持つ,すべてを疑ってかかる,物事を楽観的にしかし冷静にみる。コラムの問題は難題多し。読了しても,まだ苦手。2018/10/02
539z
1
通読2★2.破棄前。タイトルが抽象的なので気づくと思うが、「思考法」では無く「発想法」。しかも「数学的発想」の定義がこの筆者の独善的な定義で「具体的なものに接触し、体を使って体験・経験し、そこに共通に存在する法則性を見出し、自分の中に確立する「学ぶ」という活動は、数学を学ぶときに最も顕著に現れるため」というもの。ちょっとひどい。歳を取ると自然と頭が良くなる、歳下はバカだと思いこんで知ってることを知らない前提で教え込んで来て、自分の定義で突然問題を出し、正解をずらしてくるおじさんに会った時の感覚がわく2025/03/09
hwconsa1219
0
書店でタイトルに惹かれて手にしました。若干、誤字脱字があるのが気になりましたが、おっしゃっていることは常識的です。…この本のコンセプトが、数学がニガテな人に対して「こっち向かせよう」という意図だとしたら、ちと色々と不足かなぁ。2015/07/21
-

- 電子書籍
- WhiteTiger ~白虎隊西部開拓…
-

- DVD
- 襲う!!(小川亜佐美)