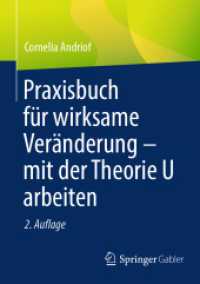出版社内容情報
困難をかかえている子どもや若者、親たちの心の声に耳を傾け、「自分が自分であって大丈夫」と語りかけるセラピー・メッセージ!
内容説明
カウンセラー30年の著者が、困難をかかえ苦しんでいる子どもや若者、親の心の声に耳を傾け、「自分で自分であって大丈夫」「ダメなあなたでもいいんだよ」と語りかけるセラピー・メッセージ。
目次
第1章 地球環境の破壊と心の問題
第2章 地球環境破壊の時代のセラピー文化
第3章 わたしの心理臨床実践と講演活動
第4章 講演 共に待つ心たち―もっとゆっくり・スローイングダウン
第5章 二つの向き合い方
第6章 共に揺れる
第7章 共に待つ
第8章 信じて、任せる
第9章 再生のセラピー文化の考え方
著者等紹介
高垣忠一郎[タカガキチュウイチロウ]
1944年高知県生まれ。1968年京都大学教育学部卒。現在、立命館大学大学院応用人間科学研究科教授。臨床心理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hideki Maeda
3
正しいものの味方、現状の日本社会や自分自身の今の考え方が良くわかりました。今見えているものや行われていることが必ずしも正しいとは限らないということ。 豊かになったことの裏で人々の失われた心がある様な気がしました。 表面的なことに囚われないようにもっと深く考察したいと思います。 その事が単純に良い悪いではなく、その問題点に向き合うことが大事だと教えてもらいました。2020/07/01
さだはる
3
主に登校拒否の子どもを持つ親に向けた内容でしたので、子どもを持たない私にはピンとこないところが多々ありでした。著者は自分をかなり自己肯定出来てるみたいだということも伝わって来ました。シニカルな感じがしなくもないが…。覚えておきたいのは「効率的でないからこそ救われる」と「条件付けられた習性が自分の世界を狭くする」です。2017/06/28
ゆう。
2
競争社会で求められるセラピー文化について考察できます。ダメな自分を否定するのではなく認めてあげることの大切さ、そのことが自分を肯定することにつながることがわかります。 とても印象に残ったのは、自分と共に生きることができない人は他社と共に生きることができないという趣旨の言葉でした。共生概念を考える上でも重要だと思いました。2013/09/06
ばんぶー
1
自分自身の価値観との戦いになります。子育てをやっていて、多分一番苦労して、結局何もできなかった、という疲労感のようなものを感じますが、この本の中には答えがありそうな気がします。ただ、私にとってこの本を読むことは、すなわち自分の価値観の見直しをすることを意味していて、大変な行程となります。2009/11/10
brawi
1
自己責任と愛国心は勝ち組・支配層のアジテーションだ。新幹線に乗ると心が後からついてくる。資本主義経済に過剰適応してスピードを求めると心が荒廃する。焦り・脅しに惑わされないようにする必要。「いのち」と私。「いのち」が私を通して生きている。2009/05/24
-

- 電子書籍
- 花×華02 電撃コミックスNEXT