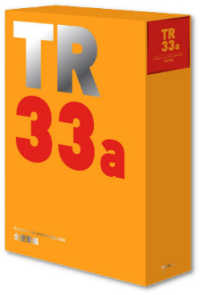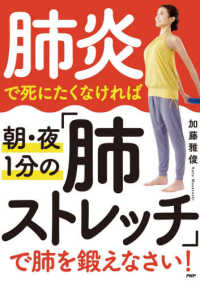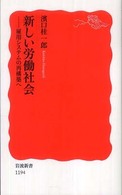内容説明
「皇室の藩屏」として明治二年に誕生し、最大九一三家を数えた華族は、昭和二十二年の新憲法施行により消滅する。誕生当初は、五位以上の公卿(清涼殿への昇殿が許された家柄)と、幕府の支配下にあった一万石以上の旧大名など、四二七家であった。その後、明治十七年の華族令制定により、「公・侯・伯・子・男」の爵位が与えられ、さらに「国家に勲功ある」勲功華族として、政治家・軍人・官僚・実業家・学者が次々と叙爵していった。華族の義務や生活、閏閥、事件、経済などの実情を通して、華族が近代日本にどのような影響をおよぼしたのかを考察する。
目次
謎で読み解く名家・名門(華族の謎20―日本の華族は諸外国と比べどのような特徴を持つのか)
天皇家を支えた華族(伊藤博文(公爵)―近代化のため華族制度を創出した維新の元勲
乃木希典(伯爵)―高潔な人格を見込まれ軍人から学習院長へ ほか)
華族の明治・大正・昭和(南部家・伯爵家―「皇室の藩屏」を貫いた生き方;山川家・男爵家―各々の功績が認められた兄弟叙爵 ほか)
華族のスキャンダル(相馬事件―開化の御家騒動;赤化華族事件―“赤き”皇室の藩屏 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
きよきよ
3
メジャーな日本の華族を家ごとに歴史を概観した本。 華族とは何かとか。 鴻池は幕府と政府両方にお金を無心されたゆえ、 今あまりお金がないらしく、気の毒に思えた。 ★★2022/04/25
中将(予備役)
1
華族についての入門的な一般書。近代の岩手を考えた時、原敬だけでなく旧藩主南部伯も偉いのだと感じた。「復活する華族社会」の章はこじつけめいてもいるが面白かった。2023/03/19
ささ
1
色々な方が書いておられるので、読みやすさに少々ばらつきがあるように感じられました。複数の華族についてとりあげられているので、この本を読んで、興味をもった人や事件などにまつわる本を、探してみようと思います。2012/10/14
k_samukawa
1
新人物文庫ではおなじみの『歴史読本』再録シリーズなのだが、これは出来がイマイチ。リーダビリティの低いものを巻頭に持ってくるのはへたくそですね。「華族のスキャンダル」の章こそ巻頭に持ってくれば良かったのに。あと、最後のまとめは的外れに思えた。2010/10/30
lop
0
華族という存在が気になって読んだのですが、自分には早かった。この本も入門編なんだろうけど、人物に全然ピンとこなくて、漠然と読んだ感じになりました( ̄▽ ̄;)今後、なにか読んだときにあぁこの本で見たわーくらいの知識になればいいかな~まあ成り立ちの流れがわかったのでよしとしたい(笑)2014/04/16