内容説明
蒙古襲来で台頭する菊池武房から、南北朝期の菊池氏の活躍を中心に、近世初頭までを生き抜いた一族興亡の歴史を貴重な史料を駆使して描く。
目次
第1章 武勇の家の系譜―大夫の監のモデルと経隆の伝承
第2章 石塁の上の男たち―『蒙古襲来絵詞』の絵解き
第3章 千本槍の伝承―菊池戦力の背景
第4章 惣領を補佐した三人―武重兄弟の活躍
第5章 十八外城の幻影―菊池諸城の攻防
第6章 肥前家と広福寺―無視されてきた人と寺
第7章 万句連歌の世界―狭間の中の一族
第8章 近世を垣間見た一族―城氏と熊本
著者等紹介
阿蘇品保夫[アソシナヤスオ]
1935年、熊本県に生れる。1958年、広島大学卒業。以降、熊本県内高校勤務。1986年、熊本県立美術館学芸課美術専門員。1995年、八代市立博物館長。現在、熊本県文化財保護審議会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
10
以前熊本歴史叢書3「中世 乱世を駆けた武士たち」を読んで知った著者1990年の書。中世九州の大族菊池氏に関する論考である。刀伊来寇から元寇を機会に武威を示し、強力な同族的結合によって肥後から肥前に渡り勢力を張る。南北朝時代は九州南朝勢力の中心となり、南朝系の武士団としては唯一室町時代まで勢力を保つが戦国時代には大友氏や島津氏の勢力に包含されて家臣団として吸収される。史実としては必ずしも確実ではないが元寇の経験から我が国の歩兵槍術戦法の祖としての姿も知った。馴染みはないが地方武士団の実像を探る好著であった。2021/11/12
-
![[ハレム]転生魔王とポンコツ勇者 ~魔王はカッコよく倒されたいのに、勇者がすぐ全滅しやがる~ 第43話 ハレム](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2110033.jpg)
- 電子書籍
- [ハレム]転生魔王とポンコツ勇者 ~魔…
-

- 電子書籍
- あなたのハニーは転生から帰ってきた【タ…
-
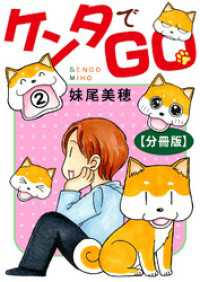
- 電子書籍
- ケンタでGO【分冊版】2 ペット宣言
-
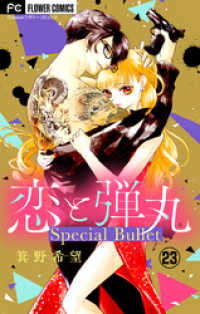
- 電子書籍
- 恋と弾丸【マイクロ】 特別編~我慢~(…





