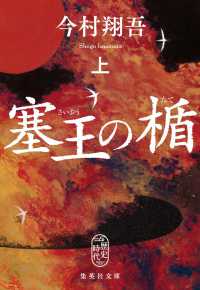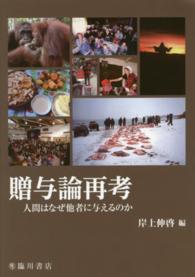出版社内容情報
利休、虎徹、そして…新たな“鬼”
幕末の名工を直木賞作家が描く!
刀、女、酒。
天才鍛冶の熱くたぎった波乱の日々!
「この刀はおれです。おれのこころです。折れず、撓まず、どこまでも斬れる。そうありたいと願って鍛えたんだ」
信州小諸藩赤岩村に生まれた山浦正行、のちの源清麿は、大石村の名主長岡家に十七歳で婿に入る。だが、武道と武具を究めようとする九つ上の兄真雄の影響で、鍛刀に興味を持ち、やがて、その熱情は妻子をおろそかにさせるほど高まろうとしていた……。
藩お抱え刀工推挙の話が頓挫した正行は、鍛えた刀を背に松代に向かうことにした。――よい刀とはなにか。道々考え続ける正行に、江戸で刀剣を学ぶ道が与えられた。紹介された窪田清音を番町に訪ねて、試斬で鍛刀の奥深さに触れた正行は、名刀への思いを強くする。そこに真田藩武具奉行の高野から声がかかり、松代の鍛冶場に入る。理想の鍛冶場を求めるうち、佐久間国忠(のちの象山)という男に出会うが……。
のちに萩藩にも迎えられ、幕末の名刀工の一人と称せられた清麿の清冽な生涯!
【著者紹介】
1999年、小社『小説NON』誌の創刊150号記念短編時代小説賞を「弾正の鷹」(同題の短編集に収録・祥伝社文庫)で受賞。選者の笹沢左保氏から、高い評価を受ける。2002年、『戦国秘録 白鷹伝』(祥伝社文庫)で長編デビュー後、04年に『火天の城』で第11回松本清張賞、09年『利休にたずねよ』で第140回直木三十五賞を受賞した。1956年、京都市生まれ。同志社大学文学部美学及び芸術学専攻卒業。
内容説明
信州小諸藩赤岩村に生まれた山浦正行、のちの源清麿は、九つ上の兄真雄の影響で作刀の道にのめりこむ。大石村の村役人長岡家に十七歳で婿に入るが、その熱情は妻子をおろそかにさせるほどたぎるのだった…。
著者等紹介
山本兼一[ヤマモトケンイチ]
1999年、『小説NON』誌の創刊150号記念短編時代小説賞を「弾正の鷹」(同題の短編集に収録・祥伝社文庫)で受賞。選者の笹沢左保氏から、高い評価を受ける。2002年、『戦国秘録 白鷹伝』(祥伝社文庫)で長編デビュー後、04年に『火天の城』で第11回松本清張賞、09年『利休にたずねよ』で第140回直木三十五賞を受賞した。1956年、京都市生まれ。同志社大学文学部美学及び芸術学専攻卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
サンダーバード@永遠の若者協会・怪鳥
文庫フリーク@灯れ松明の火
キムチ
藤枝梅安
なつきネコ