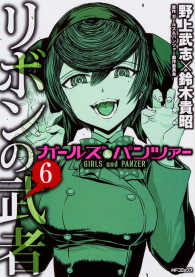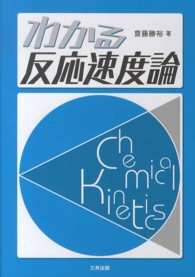出版社内容情報
考えても答えは出ません。
それでも考え続けます。
自分を自由にしてくれる
養老流ものの見方、考え方。
「わかる」とはどういうことなのか、それが「わからない」。
じゃあ説明してみましょうか、ということでこの本が始まりました。
それなら私が「わかるとはどういうことか」わかっているのかと言えば、
「わかっていない」。「わかって」いなくても、説明ならできます。
訊かれた以上は、何か答えるというのが、教師の抜きがたい癖なのです。(本文より)
学ぶことは「わかる」の基礎になる
考えることが自分を育てる
ものがわかるとは、理解するとはどのような状態のことを指すのでしょうか。
養老先生は子供の頃から「考えること」について意識的で、一つのことについて
ずっと考える癖があったことで、次第に物事を考え理解する力を身につけてきたそうです。
養老先生が自然界や解剖の世界に触れ学んだこと、ものの見方や考え方について、
脳と心の関係、意識の捉え方について解説した一冊。
八十歳の半ばを超えるまで、私は自然と呼ばれる世界を理解したかった。
若いときから、そのままでいるだけですね。
トガリネズミもゾウムシも容易に「わかる」相手ではないと思います。
本当にわかるとすれば、共鳴しかないでしょうね。
今でもそう思います。(「あとがき」より)
内容説明
考えても答えは出ません。それでも考え続けます。自分を自由にしてくれる養老流ものの見方、考え方。
目次
第1章 ものがわかるということ(代数がわからない;他者の心を理解する ほか)
第2章 「自分がわかる」のウソ(脳から考える「わかる」ということ;頭の中のさまざまな世界 ほか)
第3章 世間や他人とどうつき合うか(理解しなくても衝突しない方法;すべてが意味に直結する情報化社会 ほか)
第4章 常識やデータを疑ってみる(脳化社会は違うことを嫌う;数字が事実に置き換えられる情報化社会 ほか)
第5章 自然の中で育つ、自然と共鳴する(都市化が進み、頭中心の社会になった;自然とつき合う知恵とは ほか)
著者等紹介
養老孟司[ヨウロウタケシ]
1937年、神奈川県鎌倉市生まれ。東京大学名誉教授。医学博士。解剖学者。1962年、東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。1995年、東京大学医学部教授退官後は、北里大学教授、大正大学客員教授を歴任。京都国際マンガミュージアム名誉館長。1989年、『からだの見方』(筑摩書房)でサントリー学芸賞受賞。2003年、毎日出版文化特別賞を受賞した『バカの壁』(新潮新書)は450万部を超えるベストセラーに。大の虫好きとして知られ、現在も昆虫採集・標本作成を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
KAZOO
あすなろ@no book, no life.
tamami
ムーミン