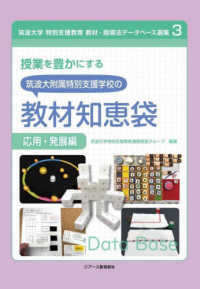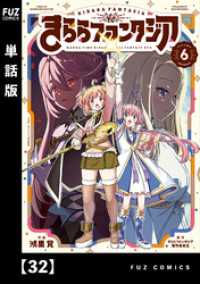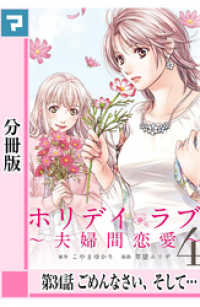内容説明
教育を受けた若者が、定職もなく街にあふれ、庶民のなけなしの預金は減る一方。景気が伸びても、給料は上がらず、物価だけ上がった。悲しいかな、これが、資本主義の本当の顔である。『資本論』をいったん遠くに放り投げた日本人は、いま再び拾い上げ、ページを開く必要に迫られている。この書には、剥き出しの資本主義が、驚くべき洞察で描かれている。資本主義の実態は、二一世紀になっても何ら変わっていない。今回、待望の『資本論』第1巻の超訳をお届けする。どうか、大著のエッセンスを味わってほしい。
目次
『資本論』第1巻(商品と貨幣;貨幣の資本への転化;絶対的剰余価値の生産;相対的剰余価値;絶対的剰余価値と相対的剰余価値の生産;労働賃金;資本の蓄積過程)
著者等紹介
的場昭弘[マトバアキヒロ]
1952年、宮崎市生まれ。神奈川大学経済学部教授。慶応義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了、経済学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
96
超訳ということで3冊に分冊されていますが、面白そうなので手に取ってみました。資本論は学生時代に岩波文庫で、その後、数十年後に「世界の名著」で読みさらには剰余価値学説史も読みました。マルキストというわけではないのですが、このような難しい本を読んでいると他の本がスラスラ読めるような気がします。この本ではかなりわかりやすく分解されていて、確かに第8章以降は当時のイギリスの状況を具体的に説明しています。私は元の本を読まずにこのような本で資本論を理解するのもありだという気がします。2023/09/25
k5
74
『資本論』のわかりやすい解説書で、とても面白かったです。「こうして、価値関係を通して、商品Bの自然形態は、商品Aの価値形態となる。あるいは、商品Bの身体は、商品Aの価値を映す価値の鏡となる」。。。これは、ある商品の価値を別の商品との関係で示した部分ですが、「自然」や「身体」という言葉が使われているのが気になりました。のちに第十七章で、労働力の商品価値を語るさいに、労働者の身体のことを語っているので、そこと関係があるのかと思いましたが、この商品Bは貨幣に帰結するんですよね。やはり『資本論』読むべきか。2020/07/25
おたま
45
「超訳」というだけあって、文庫本で3冊、1500ページもある『資本論』(第一巻)を新書1冊に要約(=超訳)したもの。『資本論』の「粗筋」を知るには手ごろだけれど、これだけで『資本論』の理解は難しいように思う。この本で、章や節の内容の方向を掴んでおいて、『資本論』本文を読んでいくと、両者ともによく分かる。私はこうした読み方をして、おおよその理解ができたと思っている。(他にも詳しく解説したものを併読していった)2022/06/01
白義
22
超訳というより、資本論のエッセンスを現代に甦らせる正統派の副読本という方が近い。物質と社会から精神や観念を明かす哲学としてのインパクトや資本論一部の中核である、労働を結晶し、元のニュアンスを失わせる「商品」の奇妙な性質は当然として、なぜ仕事がどんどん辛くなり、真面目に働いても報われず、雇用主もそんな苦境を放置するのか、という日々の悩みも是非はどうあれ現代に引き寄せた上で歴史からも説明する手腕が凄い。本訳を読むための超訳であり、読めば必ず資本論に挑戦したくなるという優れた入門書2013/11/14
えちぜんや よーた
22
資本は、最初は、多数の家内制手工業で生まれ、少数の近代的大工業にうつるが、再び多数の個別的所有に移るという説明文(冒頭のひと言)。 マルクスは「資本論」でこのような結論に至り、 後に有名な「共産党宣言」につなげたそうです(P339)。 ですが、個人的には、この「個別的所有」というのは、 単に「家内制手工業」に戻るだけなんじゃないかなと思ったりします。 参考文献は、「FabLife」と「ワーク・シフト 」 2012/09/28