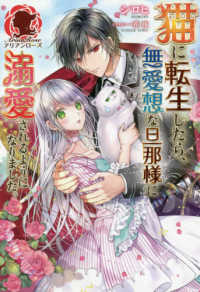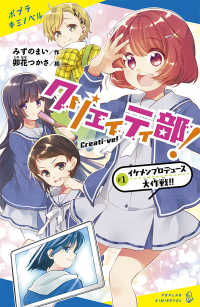内容説明
所は…宮崎県日向市駅。県・市・JR・専門家・市民の志と情熱が、まちを、人を、動かした。
目次
事の始まり 平成八年~九年
篠原委員会発足 平成十年十月
まちなかの議論 平成八年~十一年八月
危機 平成十一年十一月~十二年
再びの危機 平成十二年
塩見橋 平成十二年五月~十三年一月
木 平成十二年十月
三度目の危機、日向市失速か 平成十三年
四度目の危機、内藤・川口外し 平成十三年十月~十四年十月
商店街のまちづくり 平成十三年五月~十四年九月
木使いの実践 平成十四年五月~十六年三月
課外授業 平成十四年九月~十七年十二月
駅舎設計着々 平成十四年から十五年
追込みシンポジウム 平成十四年十一月~十五年十一月
バトンは県から市へ 平成十五年十一月~十七年二月
なかなかうまくいかない 平成十七年
駅舎着工 平成十八年
ついに開業。よくぞここまできた 平成十八年十二月十七日
その後 平成十九年一月~
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てつお
0
ひとつの駅の高架化を巡り景観デザインに取り組んだ技術者たちの話。自分達が住む地域をどう活かしていくのか、近隣の駅舎の失敗はだけは踏みたくない、という反省から始まった駅舎デザインは、周辺の人びとを巻き込み、地方都市のあり方にまで膨らんでいく。デザイナー、行政、JR、地域の子どもたちまで広がる10年にわたるストーリーは、代わる代わる登場人物たちに語られ、ある種の伝承めいてくる。これは日向市街の再生の話でもある。デザインを巡る物語が人びとを繋げ人間ドラマにまで昇華される。地元小学校で行われた課外授業が秀逸。2021/12/10
wasserbaron
0
日豊本線日向市駅の高架事業に伴う駅および駅前広場の設計と建設過程の記録。高架駅は、ともすると画一的かつ無機的な設計になる傾向があったが、日向市では建築家の内藤廣氏を招聘して、地元のイメージに合致するデザインを実現した。先行して高架化を行った際に、外国の建築士に設計を依頼した結果、デザインや使用に不具合が生じていた宮崎駅を反省材料としているところが秀逸。木材を多用した明るい環境に生まれ変わった日向市駅のデザインは高評価を受け、同駅の利用者数増加という効果もあったようである。
そうき
0
日向市駅の連立と区画整理事業において、良いものを作ろうと尽力した人々に焦点を当てたルポ。関係者自らが語り熱意が伝わってくる書き方。 文明の下僕たる土木への直接的要請にはデザイン要素が含まれない中で、価値を認めてくれるかが成功のための最大の障壁という事実がこの分野の悲しいところ。コストをかければ当然良いものができるが、そこに血税を注ぐ価値を社会が認めてくれないし、事業者も最小コストでの整備を是とする節もある。実装のために政治が必要なのがうーんみ。 完成した物の全体像がどこにも描かれていなかったのが残念。2020/10/24
-
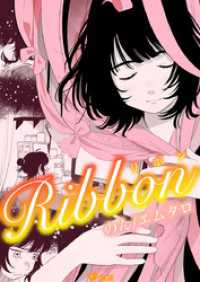
- 電子書籍
- Ribbon 15 Vコミ
-

- DVD
- 怪盗キャッツ&ハニー