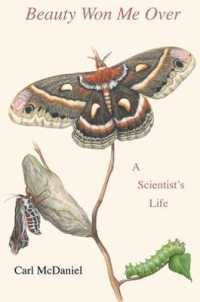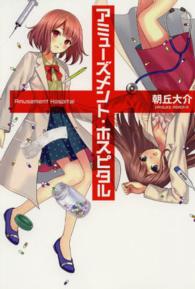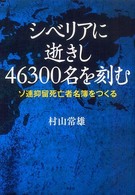内容説明
姿究極の純粋抽象をかたちづくる高度な構築性と自由な感性の融合―その奥底に潜むものは何か。“現代音楽”の地平を切り開いたアントン・フォン・ヴェーベルン(1883‐1945)の実像に迫る労作。
目次
序章 二一世紀のヴェーベルン
1 早春―作曲の試み(一八八三~一九〇二年)
2 ヴィーンで音楽学を学ぶ―大学生活(一九〇二~〇六年)
3 ミニアチュールへ―無調性(一九〇八~一四年)
4 ノン・フィニトの美学―歌曲の時代(一九一四~二五年)
5 構築性の小宇宙―鏡の国のアントン(十二音技法、一九二五年~)
6 音色の探究―編曲・改訂のプロセス
7 パトロンの素顔―パウル・ザッハー財団の資料
8 コンポーザー=コンダクターの肖像―指揮者としてのヴェーベルン
9 失速
終章 西洋音楽史のプリズム―第二次大戦後の音楽とヴェーベルン
著者等紹介
岡部真一郎[オカベシンイチロウ]
音楽学者・評論家。明治学院大学文学部芸術学科教授。東京生まれ。ケンブリッジ大学(英国)、パウル・ザッハー財団(スイス)を経て、慶応義塾大学大学院文学研究科博士課程修了。専攻は音楽学、特に20世紀音楽史。また、『日本経済新聞』『朝日新聞』『レコード芸術』『音楽の友』などで評論活動を展開し、NHKテレビ、ラジオの音楽番組の解説、キャスターなども務めている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Auristela
0
ヴェーベルンに関してかなりコンパクトにまとまった良書。何かのインタビューで、グレングールドがヴェーベルンを評して恥ずかしがり屋の音楽と言っていたが、それは言い換えれば孤独な音にも等しいだろう。孤独な音のプリズムがどのようにイジラシク輝くに至ったのか、、当時の文学との比較も面白いと思うな。2013/06/18
juntaku
0
現代音楽は理屈っぽいのは事実だが、まさに言葉の本当の意味で美的。ヴェーべルンが西洋音楽史の正統な後継者でそして後続の音楽史の流れを決める結節的に位置する作曲家であることがよくわかる。2010/11/05
-

- 洋書
- Ãœber Die…