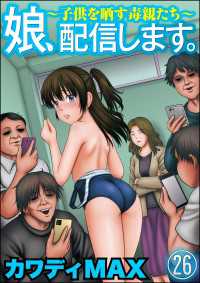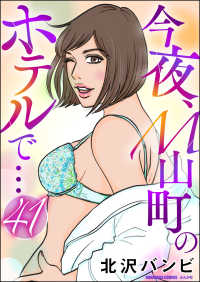内容説明
人々が古来から育んできた習俗をめぐって交わされてきた民俗知をめぐる対話。石牟礼道子、岡本太郎、網野善彦、あるいは宮本常一、柳田国男まで、偉大な先人の軌跡を丹念にたどり、民俗知の可能性について語る珠玉の論集。
目次
序章 民俗知を宿した言葉たち
第1章 石牟礼道子―苦海のほとりから(詩藻と思想とが交わる場所へ;くだもののお礼は、その先へ;聞き書きと私小説のあいだ;水俣から、福島の渚へ)
第2章 岡本太郎―泥にまみれた旅へ(もうひとつの旅学、日本へ、神秘へ;太郎と旅、東北をめぐって;前衛と生活のはざまに、旅があった;婆たちの発見の書;太陽の塔―神秘と生活のあわいに)
第3章 網野善彦―無主・無縁とはなにか(無縁という背理の時間;重戦車の孤独;無主・無縁のフォークロアは可能か;『日本論の視座』を読みなおす;網野史学、その第二楽章がはじまった;東アジア内海世界は可能か―網野善彦とブローデル『地中海』をめぐって;文字と権力と歴史と)
第4章 宮本常一―故郷と風景をめぐって
著者等紹介
赤坂憲雄[アカサカノリオ]
1953年、東京生まれ。専攻は民俗学・日本文化論。学習院大学教授。東京大学文学部卒業。2007年『岡本太郎の見た日本』(岩波書店)でドゥマゴ文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞(評論等部門)受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ジャズクラ本
20
◎ヘンテコなタイトルだが学習院の民俗学教授による評論で、その対象は石牟礼道子、岡本太郎、網野善彦、宮本常一、柳田國男。前者三人の著作は読んだことがないので、へぇ〜と感心しながら。後者二人のものはちょくちょく読んでいるのでフムフムと頷きながらの読了。特に最後の柳田國男と折口信夫の訣別のあたりは有名な話ながらも読み応え充分。もはや田舎を訪れても民俗風習が希薄になった現代。果たして民俗知は可能なのだろうか。2021/05/15
ダージリン
2
赤坂氏の著作は割と読んでいるので、内容的には既視感があるものが多い。この本で取り上げられている人達の中では、石牟礼道子さんの作品はまだ読んだことがないので、是非とも読んでみたいと思った。民俗学には強く惹かれているが、社会の変化が急速に過ぎ、習俗が失われ、過去の文化や精神性に近接していけない思いが強くある。そうは言っても、ここに取り上げられた人たちを手がかりに、新しい見方を見つけられたらと思う。2024/03/27
takao
1
ふむ2021/08/06
y
1
性食考の著者ということで手に取りました。取り上げられている5名の名前は知っていたけれど、岡本太郎と網野善彦以外は、ほぼ名前だけだったので、勉強になりました。 終章の体験/証言/記憶については、歴史のみならず日々の仕事にも当てはまるなぁと思いました。2021/02/27