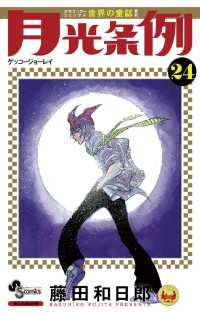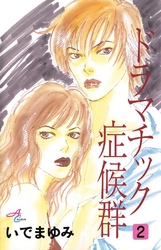- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教科指導
- > 情報・コンピュータ教育
出版社内容情報
プログラミングを子供に楽しく習得させるための必須の心得を伝授。初めて学び、教えるための待望の入門書。「簡略用語集」付き。2020年度から小学校で導入される見込みのプログラミング教育。本書はプログラミングを子供に楽しく習得させるための必須の心得を伝授。プログラミングを初めて学び、教えるための待望の入門書。「簡略用語集」付き。
上松 恵理子[ウエマツエリコ]
内容説明
2020年度小学校で必修化!!子どもにどう教えればいいの?プログラミング、ゼロからの入門書!
目次
1 プログラミングでつく新しい力
2 プログラミング言語のものさし
3 さまざまなプログラミング言語
4 プログラミングの学び方
5 プログラミングの未来
6 世界のプログラミング教育
著者等紹介
上松恵理子[ウエマツエリコ]
博士(教育学)。新潟大学大学院人文科学研究科情報文化専攻修士課程修了、新潟大学大学院現代社会文化研究科人間形成文化論専攻博士後期課程修了。現在、武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部准教授、早稲田大学招聘講師・研究員、国際大学GLOCOM・明治大学サービス創新研究所客員研究員、東洋大学・群馬大学・実践女子大学非常勤講師。「教育における情報通信(ICT)の利活用促進をめざす議員連盟(超党派)」有識者アドバイザー、総務省「プログラミング教育事業推進会議」委員など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
assam2005
22
2020年から小学校で必須になるらしい。我が子はその頃はとっくに卒業なので悔しがっていました。いくつかの候補の中からどれか言語を修得していくようですが、児童の言語との相性だけではなく、先生と言語との相性もあるので、身に付けるというよりも意識を芽生えさせるだけの様に思えました。それよりも諸外国のICT教育事情の方が驚きです。お国柄も出ていて、日本での常識が海外ではそうでないのにも驚き。SNSがほとんど実名のみの国では日本の様な問題は生じないのだろうか?2017/01/07
izw
7
ご近所会でよく一緒になる上松先生の著作を初めて読んでみました。久野先生が、プログラミングで習得できる力を挙げた後、教育用のプログラミング言語の紹介をしている。兼宗さんのドリトルも紹介されていて懐かしい。萩谷先生が「プログラミングの未来」という章でプログラミングを学ぶ意義を考察している。最後に、上松先生が海外状況を紹介している。小学校でプログラミング教育が必要か、という声もあるが、やり方さえ間違えなければ、子どもたちが熱中する教科になるだろうが、そこに導ける先生がいるか、どのように育成するかが問題だろう。2019/04/17
にこにこ
6
ものづくりの手段のひとつで、図工や技術家庭と同じかなあ。中学でも技術家庭で習っていたりするし。子どもはきっと好きだと思うし、ビジネスチャンスでもあるけど、言語習得をメインにしたら失敗する気がする。この本ならsection4は役に立ちそう。2017/03/24
かっぺ(こと悩める母山羊)
6
子供にバリバリにプログラミングできるようになってほしいとは思わないけど、仕組みがなんとなーく理解できるくらいになっていたら、便利かなあと思う。 ざくっとプログラムについて紹介されていて分かり易かった。 この本に紹介されていた「アルゴロジック」は大人もハマるパズルゲームだけれど、1年生には「ループ」を理解させるのは難しいかもしれない。「プログラミングが分からない親が家庭でどうやって教えるか」という本がでないかなー。需要あると思うけど。2017/01/16
ひょろ
3
プログラミング教育がいかに大切かを説く意味では入門書として適している。ただ、プログラミング教育の肝は「職業プログラマのようにプログラムを作る」ことではなく、プログラムを作る過程を利用して考える力、創造する力を付けることにあると思う。プログラム言語の詳細な説明とかよりも6章にあるようなプログラミング教育でどう変わっていくかに紙面をもっと割いてほしかった。2018/03/26