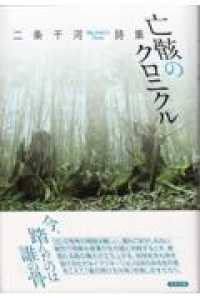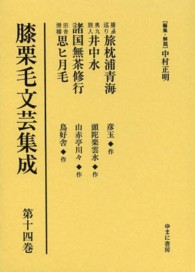内容説明
本書は、1992年4月から1993年4月にかけてサラエボで執筆された。本書は現在の記録であり、サバイバルのためのガイドであるが、同時にサラエボを戦火の犠牲地としてではなく、機知によって恐怖を克服するための実験場として伝える、未来に残る記録でもある。
目次
ダートゲーム
気候
現代サラエボ市民
インテリア
住まい
水
光
夜のサラエボ
睡眠
暖房〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きゅー
18
ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争では、数年間にわたりサラエボが包囲され、多くの市民の犠牲者を出した。この本はサラエボ包囲戦のさなかに書かれたものであり、ミシュランのガイドブックを模して、サラエボの日常を描写している。インテリア、住まい、タバコ、学校、ショッピングなどと章立てされた本文は、戦争にあっても彼らがいかに人間の尊厳を保ち、毅然と生きているかを強く印象づけた。そして、狙撃されるため道路を歩くこともできない町でコンサートが開催されたり、映画が上映されていたということの驚きはいかほどだろうか。2019/08/01
Kaorie
18
ボスニア内戦真っ只中に発売された伝説のミシュランガイドブック風のサラエヴォ案内。「サラエボ旅行案内」とかいう邦題になっているが、原題は「SARAJEVO SURVIVAL GUIDE」建物や車が炎上する写真、道路の血だまりや路上に倒れた人(多分遺体)、爆撃で廃墟と化した街、救援物資を求めて行列する人々など、鬱になること必至な写真多数、しかも当然カラー。旅行ってw無理だしw 屈折した笑いなのか、諦観の境地なのか。当時のサラエヴォを直接知らない人間はブラックユーモアに笑いつつ、読み終わってやはり鬱になった。2015/06/06
natsumi
4
1992年から始まったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の真っ只中、ミシュラン風ガイドブックの体裁で戦地の「普通の」人々の生活を内側から伝えるというプロジェクトの一環で作られた一冊。ブラックな笑いでコートされた記述とショッキングな写真が並ぶ。これは、極限状態で正気を保つためにどうしても必要なユーモアだったのだと思う。ただ、ユーゴ紛争の歴史を見ると本当に戦況が最悪になるよりも前に作られているんだよね… それがこの本の一番つらい部分かもしれない。「普通」が大事で難しいよ。2022/03/06
Mao
4
今この時にも、飢え、怯えながら暮らしている多くの人がいることを忘れてはいけないと思う。2017/01/13
arkibito
4
究極のユーモアがここにある。ユーゴ内線下、激戦が繰り広げられたサラエボ市街地。その状況を普通のガイドブックさながらに解説していく。例えば、どこの配給所がオススメだといったショッピング情報、この道はスナイパーから丸見えなので迂回すべしといった交通状況。あえて旅行ガイドという体裁をとることで、戦争の異常さバカバカしさが浮き彫りになる。実際にこれを読んでサラエボの街へ行ってしまった。2007/06/16