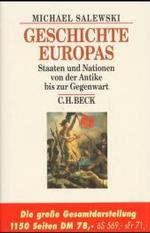出版社内容情報
「静かな退職」――アメリカのキャリアコーチが発信し始めた「Quiet Quitting」の和訳で、企業を辞めるつもりはないものの、出世を目指してがむしゃらに働きはせず、最低限やるべき業務をやるだけの状態である。
「働いてはいるけれど、積極的に仕事の意義を見出していない」のだから、退職と同じという意味で「静かな退職」なのだ。
・言われた仕事はやるが、会社への過剰な奉仕はしたくない。
・社内の面倒くさい付き合いは可能な限り断る。
・上司や顧客の不合理な要望は受け入れない。
・残業は最小限にとどめ、有給休暇もしっかり取る。
こんな社員に対して、旧来の働き方に慣れたミドルは納得がいかず、軋轢が増えていると言われる。会社へのエンゲージメントが下がれば、生産性が下がり、会社としての目標数値の達成もおぼつかなくなるから当然である。
そこで著者は、「静かな退職」が生まれた社会の構造変化を解説するとともに、管理職、企業側はどのように対処すればよいのかを述べる。また「静かな退職」を選択したビジネスパーソンの行動指針、収入を含めたライフプランを提案する。
内容説明
今、日本に新しい働き方が広がっている。「言われた仕事はやるが、会社への過剰な奉仕はしたくない」「上司や顧客の不合理な要望は受け入れない」―このような働き方に対して旧来の働き方に慣れた管理職は納得がいかず、「静かな退職者」との間に軋轢が生まれている。「静かな退職」は、非難されるべき働き方なのか、それともビジネスパーソンの「忙しい毎日」を変える福音となるのか―「雇用のカリスマ」が解き明かす。
目次
第1章 日本にはなぜ「忙しい毎日」が蔓延るのか
第2章 欧米では「静かな退職」こそ標準という現実
第3章 「忙しい毎日」が拡大再生産される仕組み
第4章 「忙しい毎日」を崩した伏兵
第5章 「静かな退職」を全うするための仕事術
第6章 「静かな退職者」の生活設計
第7章 「静かな退職」で企業経営は格段に進歩する
第8章 政策からも「忙しい毎日」を抜き去る
著者等紹介
海老原嗣生[エビハラツグオ]
サッチモ代表社員。大正大学表現学部客員教授。1964年東京生まれ。大手メーカーを経て、リクルートエイブリック(現リクルートエージェント)入社。新規事業の企画・推進、人事制度設計などに携わる。その後、リクルートワークス研究所にて雑誌「Works」編集長を務め、2008年にHRコンサルティング会社ニッチモを立ち上げる。人材・経営誌「HRmics」編集長、リクルートキャリアフェロー(特別研究員)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hiace9000
サンダーバード@読メ野鳥の会・怪鳥
mochiomochi
こも 旧柏バカ一代
逆丸カツハ