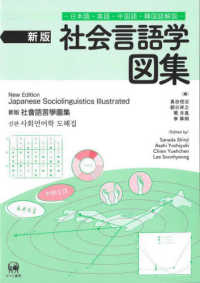内容説明
世界同時不況、格差と無意識の荒み、価値観の破壊、扁平なデジタル化、パンデミック、温暖化―様々な危機が重層的に拡大している今、私たちは何を目指して生きていくのか。いまだかつてないこの奈落の底で人智は光るのか否か。著者は、資本主義・民主主義の末期的実相に迫り、悪の正体をつかみ、より深い思索へと切り込んだ。道なき道の光明となる強靱な提言の数々。NHK番組ETV特集の独白に加筆した衝撃の名著。
目次
第1章 破局の同時進行
第2章 生体反応としての秋葉原事件
第3章 価値が顛倒した世界
第4章 無意識の荒み
第5章 人智は光るのか
第6章 “不都合なもの”へのまなざし
断想 破局のなかの“光明”について―あとがきのかわりに
著者等紹介
辺見庸[ヘンミヨウ]
作家。1944年、宮城県生まれ。早稲田大学文学部卒。70年、共同通信社入社。北京特派員、ハノイ支局長、編集委員などを経て96年、退社。この間、78年、中国報道で日本新聞協会賞、91年、『自動起床装置』で芥川賞、94年、『もの食う人びと』で講談社ノンフィクション賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
YO)))
10
<人びとを病むべく導きながら、健やかにと命じる>システム,或いは『器官のない身体』としての資本主義.外的な存在としてあるだけではなく,既に我々の内部/心性に深く根付いてしまった末期のそれに,果たして人間の生体は耐え得るのか.経済の回復を愚直(或いは浅薄)に望むのではなく,人間とはどうあるべきなのか,内面を反復して思索することこそ今求められているのではないか.真摯にして強靭な問いかけに満ちた警鐘の書.2012/09/18
魚53
5
価値があるか、儲かるか、生産性があるか。全て資本主義の尺度で測られ、蔑ろにされる人間。普段生活していて、さも当たり前かのように語られ、判断していることに疑いを挟むことの重要さ。本当にそうなのかと。言葉さえもが商売の道具にされ、上滑りの聞こえの良い言葉がもてはやされる。内実は伴っていない。マチエールという言葉。質感ということだが、デジタル化され真で正であるかのように見えるものに無いものだ。それを取り戻すこと。人間のためのシステムであってシステムのための人間ではない。言葉も同様だ。鋭い警告の書。何度も読む。2023/01/19
gilzer
4
サブプライム・ローンの破綻等を契機とする世界的金融危機。これをどう見るか。単に景気の回復だけが問題だと見る向きもあるが、著者はこれを資本主義の末期症状と捉える。ただし、経済システム論だけの問題ではない。人間性の問題でもある。つまり、問題は既に存在していたのだが、それが金融危機によって剥き出しになったにすぎない。著者の省察はラディカルな資本主義批判を基礎に持つが、それを支えるのは難解な理論や概念ではなく極めて人間的な感性であり、例えば、路上生活者に対して痛みを感じるかどうかといったことである。2013/02/07
クッシー
3
資本主義によってもたらされた価値観の崩壊について述べられている。「ことばが表意しないというか、ことばか表意するものがかつてとまったくちがっている。「エコ」や「〜にやさしい」ということばもそうですが、じつはモノを売るとか別のインテンションがある。」確かにその通りだ。言葉そのものの字面をそのまま受け止めてしまう僕にとって考えの浅さを実感させられた。こんな時代だから、人間的な価値の問い直しをすべきであると、訴えているし、それは僕も共感している。2021/12/04
MrO
3
再読。自分としてもとても怖いのは、去年は異常に見えたことが、今年は何でもなく思えてしまうことだ。ここに書かれている全ての事は、人間の生存を脅かす、とても異常なことなのだが、当たり前に身近にあるために、当たり前であるかのように思い込んでしまう。自戒する。2014/06/01
-
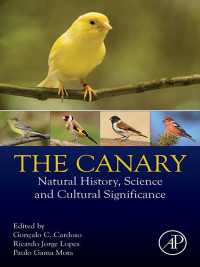
- 洋書電子書籍
- カナリア:自然誌・科学・文化的重要性<…