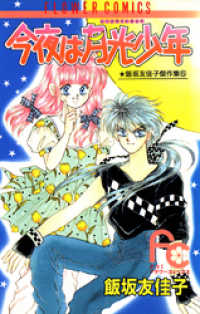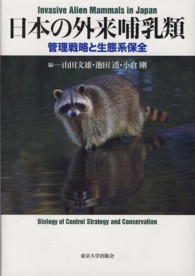内容説明
そそっかしくて落ち着きがない「ADHD」や、読み・書き・計算に支障がある「学習障害」、人との会話が成り立たない「アスペルガー症候群」などの発達障害の子どもが激増している。文部科学省の調査によると、小・中学生の普通クラスで発達障害と思われる生徒の割合はなんと6.3%。一クラスに1~2人はいるのだ。発達障害を見過ごされた子どもは引きこもりやニート、最悪の場合は犯罪者になる可能性もある。どうすれば発達障害児を見抜き、完治できるのか。発達障害を克服して医師になった著者が、発達障害児の現状から治療法までを、わかりやすく解説。
目次
第1章 子どもの発達障害を認めようとしない親たち
第2章 なぜ発達障害の子どもは親から見過ごされやすいのか
第3章 発達障害のサインに気づく
第4章 発見と治療が早ければ発達障害は克服できる!
第5章 子どもに「発達障害」について話すタイミング
第6章 発達障害の子どもと職業選択
著者等紹介
星野仁彦[ホシノヨシヒコ]
1947年福島県生まれ。心療内科医・医学博士。福島学院大学大学院教授。福島県立医科大学卒業、米国エール大学児童精神科留学、福島県立医科大学神経精神科助教授などを経て、現職。専門は、児童精神医学、スクールカウンセリング、精神薬理学など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月讀命
71
発達障害を克服し医師になった著者が、現状分析や治療法を解説。落ち着きがない。読み、書き、計算に支障がある。会話が成り立たない。ADHD。LD。アスペルガー症候群等の子供が激増している。文科省の調査では、小・中学生の普通クラスで発達障害と思われる生徒は6.3%。クラスに1~2人はいるらしい。発達障害を見過ごされた子供は引きこもりやニートになる可能性もある。しかし正しく対処すれば問題無い。モーツァルト、ベートーヴェン、エジソン、アインシュタイン、天才はみんな発達障害。トムクルーズも発達障害だったのだから。2013/12/16
大阪魂
54
遺伝とか、妊婦・出産のときや生まれてからのいろんな原因とかで脳の細胞がうまく育たへんくて、認知とか行動コントロールとか社会性とかゲットできひんなってしもてるんが発達障害。発達障害が原因で、いじめ、引きこもり、非行、犯罪、虐待の連鎖等につながることむちゃ多いそう…でもとにかく子どもさんがなるだけ小さい頃に気づいて、早く診療受けさせたら治療できる!遅くとも中学生までならだいじょぶ!って繰り返しゆーてはる本!作者自身が発達障害克服して医者にならはったそう。子どももたれる方は、早よ読んどいた方がええよーな気した…2022/10/08
佐治駿河
43
本書でも書かれているように子供の発達に気づかないのは、その親も発達障害であったことに起因する場合があるとのことでしたが、私も以前からそう感じていました。そんな親ほど健常者と一緒のクラスで勉強させたがって困りますね。そして健常者の子供たちが学校授業で苦労してしまっている話も耳にします。それと一つ疑問ですが健常者が発達障害のある方に処方される薬を飲用した場合にどのようになるのでしょうか?健常者でも集中力がましたり、記憶力が向上したりするのでしょうか?単純な疑問です。2024/11/11
ネギっ子gen
42
自らも発達障害であることを公表している児童精神科医は、関連本を多数執筆しているが、<「もっと早く治療を受けていれば……」と後悔してからでは、もう遅いのです。時間は取り戻せません。子どもの発達障害を認めず、放置すれば、子ども自身が社会不適応を起こして苦しむだけでなく、親もまた子どもの行く末を案じて、先の見えない不安な日々を送ることになってしまいます。親の「気づき」と「行動」が子どもの将来を決める/本書をお読みいただき、「もしかして」と思ったら、勇気を出して行動してください>と。一歩が、子どもの未来を救う。⇒2021/08/26
よむよむ
34
我が子が障害児(支援児)だなんて思いたくないですよね。当事者ではない私にはその思いは計り知れません。でも早い方がいいんです。本当に。問題は、認定されるかされないか微妙なところの子どもたち。対応がとても難しいです。この本では有効なヒントはあまり得られませんでした。2014/06/22