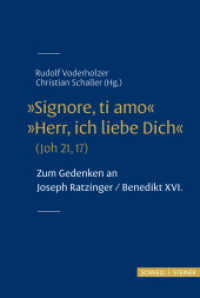- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
悲劇は今、始まったわけではない!現地を体感し続けている著者だから描ける、本当のアフガニスタン、オサマ・ビン・ラディン、そしてタリバン―。
目次
1 アメリカの一撃
2 戦争しか知らない子どもたち
3 神の戦士たち
4 オサマ・ビン・ラディンという現象
5 夏の総攻撃
6 アフガニスタンの女たち
7 カブール・日曜、午後四時の電話
8 ネイビーブルー・チルドレン
9 私は君の側にいる
10 国家、あるいは私の独立
著者等紹介
山本芳幸[ヤマモトヨシユキ]
1958年大阪生まれ。国連難民高等弁務官(UNHCR)カブール事務所所長。大阪外国語大学でヒンディー語、南アジア政治経済、国際関係論、大阪大学で法哲学などを専攻。大阪大学大学院、南カリフォルニア大学大学院、オックスフォード大学大学院で、法哲学、法の経済分析、公共経済学、日本近世政治思想史などを専攻。国連難民高等弁務官(UNHCR)、国際移住機関(IOM)、国連開発計画(UNDP)を経て、現職
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ジュール リブレ
23
国連難民高等弁務官 略してUNHCRでアフガニスタンに駐在していた山本さんの記録。事実は小説より重いものがある。善意のNGOの活動が、逆に現地の女性の威厳を損なう。悪名高きタリバンも、実態は、違って見えていたり。国連職員の不自由な生活も、また、背負っている誇りも、争いが無くならない虚しさも。「NGOは”アフガン女性をこんなに助けてます” こうやって、アフガン女性はいつの間にか女工になり、尊厳は完全に産業構造に組み込まれた」2018/08/30
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
10
2001年刊。増補版あり。著者は国連難民高等弁務官(UNHCH)カブール事務所所長。 No.1。1998年8月、著者はアフガニスタンのカンダハルにいた。そこにアメリカがビンラーディンを引き渡さないのでミサイル攻撃すると言うので人道援助の部隊は撤退。最後まで残る国際赤十字と国境なき医師団までもが。そしてパキスタンのイスラマバードへ。それから8ヵ月後にカブールに戻って来た。 No.2。アフガニスタンに物乞いはいなかった。それがこの長い内戦で出てきてしまった。アフガン人は誇り高いと言うのに。→2024/02/29
wn2IYZZWpunMUnp
1
とても良い本2019/11/29
まゆ
1
友人に進められて読んでる途中で著書のtwitterを知った。経験を通じて国家、政府、国際機関へのいろんな気持ちが芽生えたんだろう。じゃあ自分はどういう立場でどうしたいのかと言われるとよくわからない。人を救うには資金力や権力が必要なのかもしれないが、それらには面倒な制約が伴う。バランスをどうとればいいのか。2019/11/20
ShinzawaTaku
1
2000年代前半、この本のもとである著者のブログを読んでいて、色々と影響を受けた。緒方貞子さんが亡くなった時に著者の追悼文を目にし、読み直したいと思い中古本を購入。 ほぽ20年前の出来事なのだけど、今も世界中で起きている紛争と、それを取り巻く環境に様々な共通点を見つけることが出来るのではないかな。紛争の原因は個々に異なるとはいえ、政府、関係国、国連、NGOの、紛争に対する関わり方や意思決定プロセスに変化はない気もする。悲惨な目にあって死んだり難民化するのはごく普通の国民であるところも変わってないだろう。 2019/11/09
-

- 和書
- 加賀藩地割制度の研究