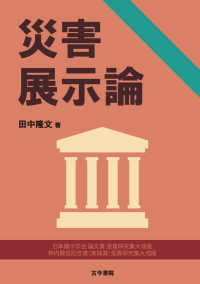出版社内容情報
《内容》 生体機能代行装置である人工臓器は,医用工学が医療にもたらした成果の一つである。実用化によって,治療法の多様化,患者の延命に大きく貢献した人工臓器のうち,本書は代謝系の人工臓器について述べている。
《目次》
1. 序論
1.1 科学技術と医療
1.2 バイオメディカルエンジニアリング(医用工学)
1.3 代謝系人工臓器
2. 人工腎臓
2.1 はじめに
2.2 腎臓の役割
2.3 人工腎臓の役割
2.4 人工腎臓の曙
2.5 人工腎臓の原理
2.6 人工腎臓の装置
2.6.1 人工腎臓システム
2.6.2 透析器
2.6.3 透析膜
2.6.4 非対称透析膜
3. 膜型人工肺
3.1 はじめに
3.2 膜型人工肺の基本デザイン
3.2.1 膜型人工肺に使用されるガス透過膜
3.2.2 対流による酸素,炭酸ガス輸送
3.2.3 血液側のガス輸送抵抗と膜抵抗
3.3 膜型人工肺の性能評価方法
3.3.1 評価方法の問題点
3.3.2 体外循環によるex vivo評価方法
3.3.3 輸送現象論に基づく性能評価
3.4 膜型人工肺のガス交換性能の改善
3.4.1 二次流れの有効利用によるガス交換性能の改善
3.4.2 蛇行管によるガス交換性能の改善
3.5 膜型人工肺の炭酸ガス除去性能
3.5.1 炭酸ガス除去膜型人工肺の概念
3.5.2 微孔性膜型人工肺の炭酸ガス除去性能
3.5.3 微孔性膜のぬれ特性と炭酸ガス除去性能
3.6 微孔性膜型人工肺における炭酸ガス促進拡散
3.6.1 炭酸ガス促進拡散の寄与
3.6.2 数値解析による炭酸ガス除去性能評価
3.6.3 数値解析によって得られた炭酸ガス除去性能
3.6.4 炭酸ガス除去性能の実験結果
3.7 膜型人工肺の長期使用
3.8 血管内留置のための外部潅流膜型人工肺
3.9 理想型人工肺を目指して
4. 人工肝臓
4.1 はじめに
4.1.1 人工肝臓開発の必要性
4.1.2 本章の枠組み
4.2 肝臓について
4.2.1 肝臓の構造と機能
4.2.2 肝臓病とその治療法の概要
4.3 人工肝臓について
4.3.1 人工肝臓の目標と分類
4.3.2 人工肝臓開発の変遷
4.4 ハイブリッド型人工肝臓
4.4.1 ハイブリッド型人工肝臓の必要条件とその設計の考え方
4.4.2 ハイブリッド型人工肝臓に利用する肝細胞
4.4.3 ハイブリッド型人工肝臓に用いるスカッフォルド(肝細胞付着用の足場)
4.4.4 肝細胞の培養方法
4.4.5 ハイブリッド型人工肝臓モジュールの設計
4.4.6 本節のまとめ
4.5 スフェロイドを用いたハイブリッド型人工肝臓の開発
4.5.1 PUF・スフェロイド培養法の確立
4.5.2 人工肝臓モジュールのスケールアップの実際
4.5.3 体外循環システム
4.5.4 本節のまとめ
4.6 ハイブリッド型人工肝臓のヒト臨床への適用例
4.7 おわりに
5. 人工膵臓
5.1 はじめに
5.2 糖尿病の分類
5.2.1 インスリン依存型糖尿病(1型糖尿病)
5.2.2 インスリン非依存型糖尿病(2型糖尿病)
5.3 膵島
5.3.1 人工膵臓
5.3.2 ハイブリッド型人工膵臓
5.3.3 グルコースセンサを用いた人工膵臓
5.4 グルコースセンサの基礎原理
5.4.1 酵素反応と電気化学計測
5.4.2 酵素反応速度と基質濃度
5.4.3 固定化酵素膜の拡散と反応
5.5 生体計測に必要な事項
5.5.1 皮下組織液のグルコース濃度
5.5.2 生体データ
5.6 グルコースセンサの膜デザイン
5.6.1 グルコース感応膜
5.6.2 選択透過膜
5.6.3 膜透過特性の測定理論
5.6.4 膜の選択透過性
5.6.5 制限透過膜
5.6.6 生体適合膜
5.7 皮下埋込みグルコースセンサの進展
5.7.1 複合膜のセンシングモデル解析
5.7.2 針型先端感応式センサ
5.7.3 針型側面感応式センサ
5.8 マイクロダイアリシス採取型連続血糖値モニタ
5.8.1 マイクロダイアリシス法
5.8.2 マイクロダイアリシス法グルコース計測
5.9 血糖値モニタの進展
5.9.1 メディエータ型簡易血糖値モニタ
5.9.2 銀電極還元電流型血糖値モニタ
5.9.3 酸素発生型簡易血糖値モニタ
5.10 携帯型人工膵臓
5.11 新規なグルコース・血糖値測定法
5.12 ハイブリッド型人工膵臓
5.13 今後の課題
6. 薬物送達システム
6.1 はじめに
6.2 血中濃度と標的濃度
6.3 薬物の生体膜吸収
6.3.1 拡散係数と分z係数
6.3.2 2層膜モデル
6.4 体内動態
6.5 制御放出
6.5.1 マトリックス型製剤からの薬物放出
6.5.2 レザバー型製剤からの薬物放出
6.6 DDSに用いられる高分子基剤
6.6.1 非分解性高分子
6.7 DDSの現状
6.7.1 経口DDS
6.7.2 経皮治療システム
6.7.3 眼科領域のDDS
6.7.4 プロドラッグ
6.7.5 気道,鼻粘膜からのDDS
6.7.6 薬物ターゲティング
6.8 時間治療と時間制御型DDS
6.9 DDS設計におけるバイオミミクリー
6.10 将来の展望
内容説明
現在臨床応用されている人工臓器と研究されている人工臓器の種類は、人体のほとんどをカバーするほど多い。人工臓器をその機能で大きく分けると、循環系と代謝系があり、本書では代謝系人工臓器を解説している。
目次
1 序論
2 人工腎臓
3 膜型人工肺
4 人工肝臓
5 人工膵臓
6薬物送達システム
著者等紹介
酒井清孝[サカイキヨタカ]
1965年早稲田大学理工学部応用化学科卒業。1970年早稲田大学大学院博士課程修了(化学工学専攻)。工学博士。1970年静岡大学専任講師。1972年静岡大学助教授。1973年早稲田大学助教授。1978年早稲田大学教授、現在に至る。1983年Cleveland Clinic人工臓器研究所客員教授。1990年University of Texas at Austin客員教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。