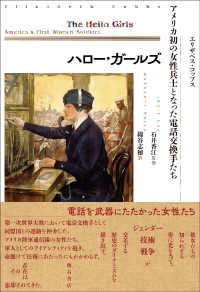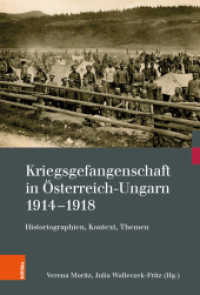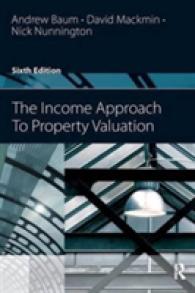目次
授業による子どもの変革
授業での創造と発見
授業での否定と発展
授業の中でのコミュニケーションの拡大
格調の高い授業
教材の解釈
芸術的要素を持った展開
授業や芸術教育から生まれた子ども
学校でしかできないもの
著者等紹介
斎藤喜博[サイトウキハク]
1911年3月20日群馬県佐波郡芝根村川井に生まれる。1923年3月芝根尋常高等小学校尋常科を卒業。4月高等科に入学。1930年3月群馬師範学校を卒業。4月佐波郡玉村尋常高等小学校へ赴任。1932年6月アララギに入会し、「アララギ」に短歌を発表。1943年3月芝根村国民学校へ転任。1946年6月歌誌「ケノクニ」を創刊。1947年4月玉村中学校へ転任。1949年12月群馬県教職員組合常任執行委員となる。1952年3月教育科学研究会の結成に参加。県教組文化部長任期満了。4月佐波郡島村小学校校長に就任。1963年4月前任校長の急死により急遽境町東小学校に転任。1964年4月境小学校校長に転任。10月教育科学研究会に教授学部会を創設。1965年8月教育科学研究会全国集会に教授学分科会を開設。1969年3月境小学校校長を退職。1973年11月教育科学研究会をはなれて、教授学研究の会を結成。1974年8月宮城教育大学授業分析センター専任教授に就任。1975年3月宮城教育大学を退任。1981年6月教授学研究の会会誌『事実と創造』を創刊。7月24日没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kohei Fukada
Toshiyuki Fukushima
rigmarole
祐亮池住
Takuo Iwamaru