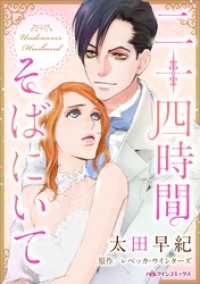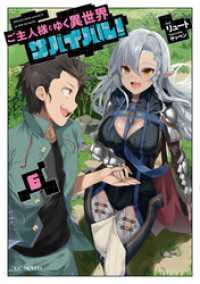内容説明
近代は何を狂わせたか―“異”なるものの復権。探偵小説がいかに“狂気”を描いたかを読み解き、近代という時代に潜む文化と制度の裡面、そして文学によってなされた企みを明らかにする。
目次
第1部 心身における“狂気”(狂信という心理―小栗虫太郎「後光殺人事件」;“狂気”を孕む身体―夢野久作「ドグラ・マグラ」)
第2部 “狂気”を内包する場(精神病院法のもたらす探偵/犯人像の構築―大阪圭吉「三狂人」;戦後社会への批判としての“狂気”―大下宇陀児・水谷準・島田一男「狂人館」)
第3部 法制度と“狂気”(精神鑑定という罠―平林初之輔「予審調書」;自白の追求という“狂気”―小酒井不木「三つの痣」;夢遊病と犯罪をめぐって―浜尾四郎「夢の殺人」)
第4部 “狂気”表象の歴史性(“狂気”の物語の発掘―岡本綺堂「影を踏まれた女」;精神医学に復讐する狂女―夢野久作「笑ふ〓女」;佯狂表象の物語―岡本綺堂「川越次郎兵衛」)
第5部 仕掛けとしての“狂気”(ミスリードと“狂人”―江戸川乱歩「緑衣の鬼」;探偵行為としての精神分析―木々高太郎「わが女学生時代の扉」)
著者等紹介
鈴木優作[スズキユウサク]
神奈川県生まれ。立教大学大学院文学研究科博士前期課程修了、成蹊大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。『新青年』研究会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
102
謎解きを主眼としない「変格」探偵小説について、従来は怪奇幻想やエログロ要素を含むものとされてきた。そうした側面もあろうが、普通の人が無意識に避けてきた「狂気」の視点から再評価する。科学的な思考が行き渡らず戦争と不況に沈んだ戦前は、人の異常な言動を合理的に判断するより狂気に憑かれていると考える方が理解しやすかった。芥川や太宰も狂気を扱った小説を書いており、狂気とは作家が時代の不安な空気を表現する手段だったのだ。文学史研究としても面白い考え方で、取り上げられた作品をまとめて「狂気ミステリ傑作選」にならないか。2022/04/08
longscale
6
連休をいいことに図書館で借りたハードカバー。一章一作品ずつ論じるスタイルになっていて、全12作のほとんどが青空文庫にある。未読の作品は同時進行で読んだ……。残念ながら思っていたのと違い、時代背景を指摘する社会科学的なアプローチが色濃い。新宗教ブームや公立精神病院の設立経緯などを紹介し、当時の狂気・狂人観を明らかにしたりする。他方で文芸評論としては当たりハズレがあり、物足りないものも多い。総じて意外性には乏しく、腑に落ちないテクスト解釈も……。知識は得られるし、語り継ぐべきテーマだとも思うが、読者を選ぶ本。2021/07/25
あんすこむたん
5
内容が濃いが、やや扱いに困る著書。というのも谷口基の評論を参考にして、論じていることは美点であり、ミステリー好きでもなかなか手を出さないタイプのものをうまく評論としてまとめている。ただし、作品というより、時代背景が主点で詳しく知ろうとしてない読者にとっては、ややつらいところがある。2022/03/26
おちこち
2
様々な探偵小説における「狂気」の描かれ方を読み解いた評論。狂気と一口に言っても論理・合理主義に比較されるものだけでなく、社会における法制度の変化や精神科学・精神分析との関わりが論じられている。 また、狂気というモチーフを通して探偵小説の新たな側面を伺えるのがとても興味深かった。2022/04/10
ヤマニシ
2
「<狂気>を通じて探偵小説を読み解くことは、探偵小説が内包する時代に対しての批評性を浮き彫りにすることにも繋がるのである。」(p23)2021/04/28