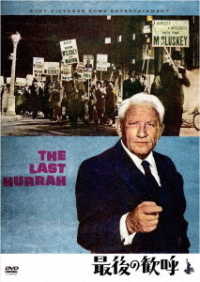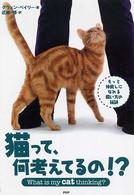内容説明
『羅生門』から新たな歴史が始まった。1950年8月26日の劇場公開以来、日本映画の水準の高さを世界に知らしめた傑作『羅生門』。企画から撮影、宣伝公開、世界展開にいたるまで色褪せることのないその魅力を多角的に徹底解剖。世界初紹介の資料多数収録!
目次
第1章 企画と脚本
第2章 美術
第3章 撮影と録音
第4章 音楽
第5章 演技
第6章 宣伝と公開
第7章 評価と世界への影響
黒澤明『羅生門』の空間と構成
IT‐One Quest開発の経緯
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
keroppi
68
昨年、国立映画アーカイブで開催された「羅生門展」の図録。図書館に予約していたら、今頃になって回ってきた。展示で見た後に、映画も見返しており、展示で見た実物や映像を思い出しながら読む。改めて、この映画の凄さを実感する。なんと言っても、この映画のテーマ性が色褪せない。現在の社会状況や国家間のやり取りを見ていると、まさに羅生門的な藪の中の事象の多いこと。若き黒澤明や橋本忍や宮川一夫や早坂文雄や、その他スタッフ、役者たちの圧倒的な才能が輝かしいばかりの光を放っている。その光の反射を、この本で感じ取ることが出来る。2021/03/17
ぐうぐう
23
公開70周年を記念して国立映画アーカイブで開催中の『映画『羅生門』展』の公式図録。初紹介となる資料が多く収録されている。準備段階や撮影現場のスチール写真も見応えがあるが、宮川一夫と野上照代の撮影台本がひときわ目を引く。70年も前に撮られた映画ゆえに、関係者のほとんどが物故される中、スクリプターの野上と録音技師助手の紅谷愃一へのインタビューも貴重な証言だ。読後、久しぶりに『羅生門』を観直してみた。世界が黒澤明を発見するきっかけとなった『羅生門』だが、橋本忍の革新的なシナリオ、(つづく)2020/11/04
えふのらん
1
京都文化博物館の展示ついでに買った。冒頭で杣売が森を歩く場面にけっこうなスペース(ページ)が割り当てられていて面白い。例の大鏡の他にも歩く杣売とカメラ、それを運ぶレールの配置を具体的なショットを並置しながら図説していて、被写体にロールしながら回り込むシーンがどのように撮影されていたかがわかる。(黒澤作品の他にもにも鴛鴦歌合戦などでも採用)よく見るとカメラに向かってきた被写体にレールを跨がらせて、斜め方向に見逃すみたいなこともやっていおり、宮川一夫の空間把握能力にゾッとさせられた。2021/02/20
ルーシィー
0
映画、羅生門が大好きなので。2021/08/16
-

- 洋書電子書籍
- 海洋環境における微小プラスチックのリス…