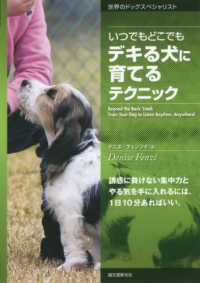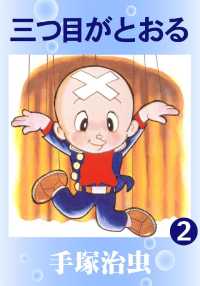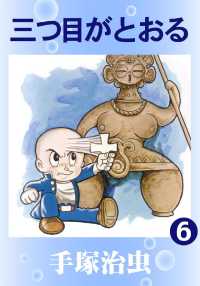出版社内容情報
戦前期の日本で初めて保育に導入され、教育現場での紙芝居活用を決定づけた「幼稚園紙芝居」シリーズをオールカラーで収録。戦前期の日本で、初めて保育に導入された紙芝居の実相とは?――。教育現場での紙芝居活用を決定づけた「幼稚園紙芝居」シリーズを中心に、外国文学の受容史やメディアでの位置づけなど、多面的な視点から紙芝居を取り上げ、研究の基盤となる資料を提示する。
■本書の特徴
・「教育紙芝居の創始者」とも呼ばれる高橋五山による最初期の教育紙芝居「幼稚園紙芝居」。所蔵する機関が極めて少ない、その全30作品を網羅。ほぼ全ての絵と脚本をオールカラーで収録し、詳細な解説を付す。
・脚本や絵の特徴、題材の出所、演出方法や、他の児童文化財との比較、戦後の紙芝居運動とのつながりなど、幅広い視点から解説を付し、紙芝居研究への新たな視座を提示する。
・「ゆっくり抜く」「さっと抜く」や「半分とめて二枚の絵を組み合わせる」など、初めて演出方法が記された紙芝居であり、紙芝居の実演、読み聞かせなどを行う教育者にとっても、演出の歴史を学ぶ上で有用である。。
・巻末には、各分野の研究者による論考と、高橋五山および児童文化に関する略年譜を付す。
[収録紙芝居]
第1部 童話の紙芝居化と保育への導入
赤ずきんちゃん/花咲ぢぢい/長靴をはいた猫/金の魚/付録 カヘルトウシ/大国主命と白兎/付録 お猿とめがね/とんまなとん熊/三匹の仔豚/かぐや姫/ふしぎの国アリス物語/鴨とり権兵衛
第2部 紙芝居における演出技術の深化
ピーター兎/おむすびころりん/軍用犬のてがら/烏勘兵衛/七匹の小山羊/ハンスの宝/コブトリ/赤んぼばあさん/熊のお家/ピョンちゃんのお使
第3部 戦争の激化と新たな紙芝居への模索
オニノツリハシ/スズメノオヤド/ネズミノヨメイリ/森の幼稚園 オベンタウ/ケンミン(健民)/ヨクバリイヌ/ベニスズメトウグヒス/クウシウ(空襲)/金太郎の落下傘部隊/ガンバレコスズメ
[収録コラム]
紙芝居の裏面の工夫
大村主計と童謡
浜田広介について
全甲社編集部の仲間たち
幻灯のアリス
全甲社の紙芝居舞台と幕絵
目白文化村と落合文士村
「動くマンガ」のアイデア
ペープサートとパネルシアター
五山の能楽・狂言への興味
紙芝居の演じ方の変遷
はり絵紙芝居と保育 ほか
[論考・年譜]
『三匹の仔豚』と『ピーター兎』 ――西洋童話の受容史からみた「幼稚園紙芝居」の革新性(川戸道昭)
教育紙芝居になった神話と昔話(日本篇)――高橋五山の選択(三浦佑之)
戦後における紙芝居とその教育的利用――保育紙芝居を中心に(米村佳樹)
保育紙芝居の歴史――高橋五山を中心として(高橋洋子)
高橋五山・児童文化史年譜
高橋洋子[ タカハシヨウコ ]
川戸道昭[カワトミチアキ]
三浦佑之[ ミウラスケユキ ]
米村佳樹[ ヨネムラヨシキ ]
目次
第1部 童話の紙芝居化と保育への導入―幼稚園紙芝居 第一輯~第十輯(赤頭巾ちゃん;花咲ぢぢい;長靴をはいた猫 ほか)
第2部 紙芝居における演出技術の深化―幼稚園紙芝居 第十一輯~第二十輯(ピーター兎;おむすびころりん;軍用犬のてがら ほか)
第3部 戦争の激化と新たな紙芝居への模索―幼稚園紙芝居 第二十一輯~第三十輯(オニノツリハシ;スズメノオヤド;ネズミノヨメイリ ほか)
論考・年譜
著者等紹介
高橋洋子[タカハシヨウコ]
1961年群馬県生まれ。2007年から紙芝居研究に取り組み、2011年より高橋五山の紙芝居の復刻出版を手がける。日本ルイスキャロル協会、仏教文化におけるメディア研究会(大正大学)、佛教文化学会会員
川戸道昭[カワトミチアキ]
1948年群馬県生まれ。中央大学理工学部教授。1971年慶應義塾大学法学部卒業。79年中央大学大学院文学研究科英文学専攻博士課程満期退学。92年イギリス・ヨーク大学客員研究員(94年まで二年間)
三浦佑之[ミウラスケユキ]
1946年三重県生まれ。立正大学文学部教授。1966年成城大学文芸学部卒業、75年同大学院博士課程単位取得退学。共立女子短期大学、千葉大学教授を経て現職。『村落伝承論』で第五回上代文学会賞、『口語訳古事記』で第一回角川財団学芸賞を受賞
米村佳樹[ヨネムラヨシキ]
1949年福岡県生まれ。四国大学生活科学部教授。1977年広島大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。四国女子大学短期大学部講師を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。