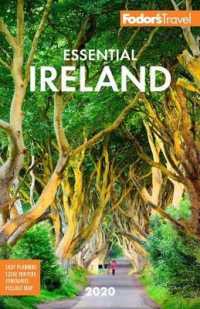内容説明
「憲法学者」とは何だったか、これから何であり得るか。その出自において「戦後」性と切り離せない日本国憲法と、その担い手となった憲法学者たち。しばしば「抵抗」の物語として理解―あるいは誤解―されてきた「学知」の忘れられし多様さを、歴史的かつ多角的に描き出す。
目次
「戦後憲法学」とは何か
第1部 「戦後憲法学」の形成(「戦後憲法学」の誕生―「啓蒙」と「抵抗」;日本国憲法の「定着」をめぐって―憲法調査会と憲法問題研究会;「戦後憲法学」の多様化―戦後日本における「保守」憲法学の展開)
第2部 「戦後憲法学」の担い手(「東大学派」の系譜―法と政治の間で;「京大学派」の系譜―理論と実践の交錯;「理論憲法学」の再興―樋口陽一と立憲主義の復権)
第3部 「戦後憲法学」の舞台(「戦後憲法学」と平和主義―九条という「主戦場」;「戦後憲法学」の死角―沖縄、マイノリティ、アジア)
これからの憲法学を考えるために
著者等紹介
鈴木敦[スズキアツシ]
北海道大学大学院法学研究科准教授
出口雄一[デグチユウイチ]
桐蔭横浜大学法学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
わんぱら
1
戦後憲法学の多様性を示す本。「抵抗の憲法学」という描像に対抗する第一部は、その成立及びその外部との対比が明確。しかし、「東大学派」「京大学派」を検討する第四章・第五章は、それぞれの関係者にもいろいろいますよ、と示すに留まる印象。それはそうだろうけど、それでもなお、というのが知りたかったが、紙幅の限界。とりわけ、東大学派について、それが権威主義的に見える部分を指摘しながら、それを整理せずに、東大学派があるとすればそれは「「自由」と「寛容」を愛し「権威主義」を憎む」ものと特徴づける(144)のは謎だった。2021/09/18
check mate
0
「東大関係者が圧倒的なマイノリティである世間」(154頁)はさすがにリアルにお茶を噴いた2023/04/02