内容説明
本所五間堀の「鳳来堂」は、父親が営んでいた古道具屋を、息子の長五郎が居酒見世として再開した“夜鳴きめし屋”。朝方までやっているから、料理茶屋や酒屋の二代目や武士、芸者など様々な人々が集まってくる。その中に、かつて長五郎と恋仲だった芸者のみさ吉もいた。彼女の息子はどうやら長五郎との間にできた子らしいが…。人と料理の温もりが胸に沁む傑作。
著者等紹介
宇江佐真理[ウエザマリ]
1949年函館生まれ。函館大谷女子短期大学(現・函館大谷短期大学)卒業。’95年「幻の声」でオール讀物新人賞を受賞。2000年『深川恋物語』で吉川英治文学新人賞、’01年『余寒の雪』で中山義秀文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





時代小説大好き本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ
123
鳳来堂は、元々は古道具屋をしていた家だった。両親去り、居酒見世に鞍替えした。息子の長五郎が独り営む見世。鳳来堂の続編である。独り者の現代であれば夜の世界を居酒屋より垣間見ながら思索に更ける様が、江戸の町と共に良い意味で鬱と描かれている。しかし、結末はそうに在らず。あまり僕が好きでないタイプのみさ吉は言う。てて親だっていうことは一生ついて回るのよ、と。そうだね。僕も今年は愛息誕生に接し、不思議な感覚だったのが、段々変化している途上の心情だからか沁み入りました。2015/12/15
ぶち
121
大学受験の勉強をしていた高校3年生の頃、父親が夜鳴き蕎麦や夜鳴きラーメンを差し入れてくれたり、夜遅くに深夜営業しているお蕎麦屋さんや屋台の居酒屋に連れ出してくれました。未だ小娘だった私ですが、大人に囲まれて食事をとっている間に、すかっり深夜の外食の楽しさに嵌ってしまいました。いまだに夜遊び好きの癖が抜けません。本書は、夜から明け方だけ営業している居酒屋が舞台です。疲れた心身を癒してくれるお店の良さがひしひしと伝わってきます。人情と美味しそうな料理、深川/本所の風情がいっそうと楽しませてくれます。2021/05/04
佐々陽太朗(K.Tsubota)
112
『ひょうたん』の後日譚。年の瀬に聴く落語に『芝浜』がふさわしいとすれば、『ひょうたん』と『夜鳴きめし屋』は年の瀬に読むならこの本といった風情がある。手際よく作った小料理にほどよい燗酒。店には気が置けない常連たち。まことによろしい。料理を作る場面の記述はほどんどレシピとして使えるほど。「鰯のかまぼこ」と「鰯の三杯酢」は作ってみたい。というか、それをアテにぬる燗の酒などやってみたい。あぁ、たまらん・・・2014/12/20
じいじ
93
いいです、泣かせます、心が和みます。宇江佐真理の人情物語。できれば少し早く大晦日の除夜の鐘音を聴きながら読了したかった。舞台の居酒屋「鳳来屋」は、亡き父親の古道具屋を見切って改装して開いた店。独り者の主人長五郎が、唯一心を惹かれて抱いた芸者との、十年の時を経て芽生える恋の話である。宇江佐さんの描くほんのり切なく、温かい恋の話は素敵です。大好きです。好きなのに「好きだ」と言えないシャイな長五郎が歯がゆいが格好いいです。客の顔ぶれも気風いい江戸っ子ばかり。清々しいエンディングで読了感も満点。傑作の一冊です。2016/01/18
ふじさん
92
父親が営んでいた古道具屋を息子の長五郎が居酒見世として再開した「夜鳴きめし屋」は、朝方までやっている店で料理茶や酒屋の二代目、武士、大工、芸者等、様々な人々が集まる店だ。今だに一人者の長五郎だが、かつては恋仲だった芸者のみさ吉とは、妾となり縁が切れたが、連れ合いを亡くし、再び長五郎との繋がりが生まれる。みさ吉の一人息子の実は長五郎ということも分かり、最後は幸せな結末を迎える。市井の人々の日常を一組の男女の恋話を絡めて描いた、人々の人情と美味しそうな料理の温もりが心地良い作品。2023/11/09



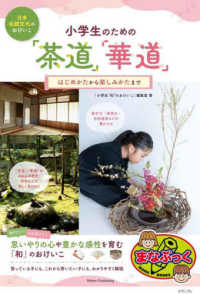
![逮捕しちゃうぞ 〈3〉 - [TVアニメ・シリーズ] <VHS>](../images/goods/ar2/web/imgdata2/40630/4063065979.jpg)


