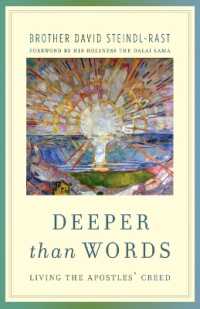内容説明
「ぼくたちはルソーの語る意味での主権者なのだろうか、それともルソーが嘲笑したように、選挙のあいだだけ自由になり、そのあとは唯々諾々として鎖につながれている奴隷のような国民なのだろうか」(訳者あとがき)。世界史を動かした歴史的著作の画期的新訳。
目次
社会契約論(最初の社会;最強者の権利について;奴隷制度について;つねに最初の合意に溯るべきこと;社会契約について ほか)
ジュネーブ草稿(社会体の基本的な概念;法の制定;国家法または政府の制度)
著者等紹介
ルソー,ジャン=ジャック[ルソー,ジャンジャック][Rousseau,Jean‐Jacques]
1712‐1778。フランスの思想家。スイスのジュネーヴで時計職人の息子として生まれる。16歳でカトリックに改宗。家庭教師等をしながら各地を放浪し、大使秘書を経て、37歳で応募したアカデミーの懸賞論文『学問芸術論』が栄冠を獲得。意欲的な著作活動を始める。『人間不平等起源論』と『社会契約論』で人民に主権があると主張し、その思想はのちのフランス革命を導くこととなった
中山元[ナカヤマゲン]
1949年生まれ。哲学者、翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
56
E図書館。人間が生存するためには、集まることによって、抵抗を打破できる力をまとめあげ、ただ一つの原動力によって働かせ、一致した方向に動かすほかに方法はない。まとめ力は、多数が協力することでしか生まれない。しかし自己保存手段は、各人の力と自由(39頁)。主権とは、一般意志によって導かれる力こそ主権と呼ばれる。しかし国家の公的人格のほか、私的な人格も考慮にいれる必要がある。市民の権利と主権者の権利を明確に区別することが大切。市民が国民としてはたすべき義務と、市民が人間として教授できる自然権を区別すること2022/10/08
かわうそ
51
「軍務のように固有の才能…」が必要なものは抽選ではなく選挙にすべきであるというが、確かにルソーの言うように行政の裁量が極限までに抑えられているという条件では行政の長を抽選で決めるというのは正しい。しかし、ルソーのように初期の国民国家においては裁量の範囲を狭めることは可能でした。国家が狭ければ裁量権が広く認められる必要がないからです。ゆえに裁量の範囲は当たり前に狭かったのです。現在、国家機構自体が膨張してるのであって行政の裁量というのは広いのですから、裁量の広い行政の長を抽選で決めることは危険をである。2022/03/31
かわうそ
44
『部分的な結社が存在するときには、ソロン、ヌマ、セルウィウスが行ったように、結社の数を増やして、不平等が発生するのを防ぐ必要がある。こうした周到な配慮こそ一般意志がつねに輝きを失わず、人民が欺かれないための唯一の良策なのである。』67ページ。部分的な結社が存在してしまっている日本において部分的な結社を増やさないという選択肢はない。この結社は政党という意味でも取れるし、中間団体的な結社という意味合いでも取れる。中間団体を活発化させることが政治の腐敗を防ぐことになるのではないでしょうか???2022/11/27
ころこ
44
社会契約論では、国家の秩序をつくる法を決める決議が、各人の特殊意志の総和によるのではなく、一般意志として示されることが、その国家にとって良いことである。国家に入った瞬間に一般意志に従うというメタ規則である社会契約に従うというにより、国家にいるということは一般意志に従わなければならないという強制が働く、という明快なメカニズムが示されています。ルソーが中途半端に考えていないのは、これが共同体のことではなく国家のことであるとしていることと、決議に関することが立法であって、行政のことは別途、民主制、貴族制、君主制2019/03/19
かわうそ
43
何度でも読みたい。法は平等と自由を土台とすべきである。平等は侵害されることが常なのだから、法は平等を保護するようにしなければならない。なぜなら平等と権利の対義語は力であるからだ。力とは膨張、拡大するものであり、拡大するものは他のものを餌として食らう。その餌とは権利、平等である。だから、平等は法によって守られるべきものなのだ。そして、法の根幹をなすのは社会契約である2024/06/13
-
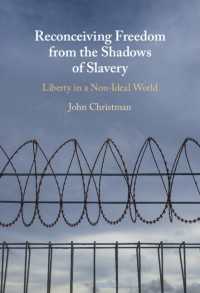
- 洋書電子書籍
- Reconceiving Freedo…
-
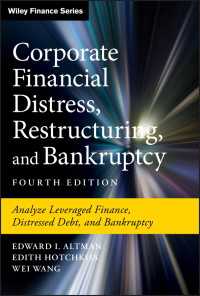
- 洋書電子書籍
- 企業の財務危機、再建と破産(第4版)<…