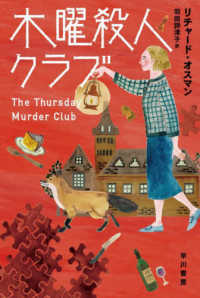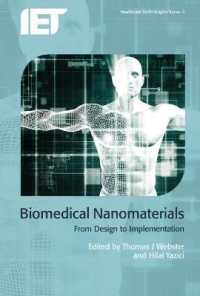出版社内容情報
近年、政治の世界ではデータやファクトにもとづいた政策形成の流れができており、「EBPM(Evidence Based Policy
Making)」と呼ばれている。しかし実際にはヘンな政策ばかり実現されるし、時間と費用の無駄ではないかといった疑問は残る。いったい私たちはどのように政策を考え、評価すればよいのだろうか? 専門家じゃなくてもスルスル読めて、関係者にはグサッと刺さる。気鋭の学者が届ける政策のあたらしい見取り図。
内容説明
近年、政治の世界では「エピソード・ベースからエビデンス・ベースへ」という掛け声のもと、データやファクトに基づいて政策を作り、評価する流れがある。EBPM(Evidence‐Based Policy Making)とも呼ばれるこうした政策のあり方は、いかなる背景から生まれたのか。先駆けである英米の潮流や、EBPM以前の日本にも存在した合理的な政策と評価を目指す動きとは。そもそも、エビデンスとは何を指し、どのように扱えば有益なのか。私たちが見落としがちなこととは。そして、日本の政策はどうすれば十分に機能するのか。公共政策学の知見からエビデンスと政策の関係を整理した待望の一冊。
目次
第1章 EBPMの出現
第2章 日本における政策評価
第3章 日本におけるEBPM
第4章 エビデンスを掘り下げる
第5章 政策の合理化はなぜ難しいのか
第6章 EBPMのこれから
著者等紹介
杉谷和哉[スギタニカズヤ]
1990年大阪府生まれ。京都府立大学公共政策学部公共政策学科卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学。博士(人間・環境学)。京都文教大学非常勤講師、京都大学大学院文学研究科特定研究員などを経て、現在、岩手県立大学総合政策学部講師。専門は公共政策学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
-





Hr本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
msykst
とある本棚
zunzun
素人
-
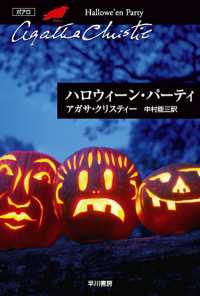
- 電子書籍
- ハロウィーン・パーティ クリスティー文庫