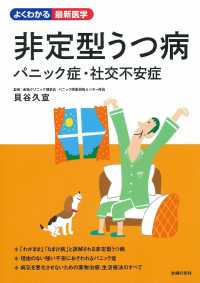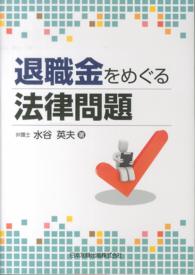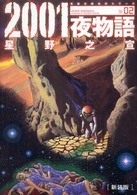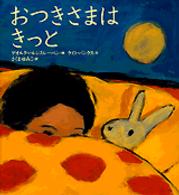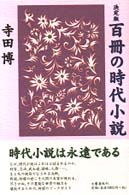内容説明
悲しいことだが、古今東西、人類の歴史は戦争の連続であった。有史以来、世界で戦争がなかった年はわずか十数年だという学者もいる。戦争の原因は、さまざまなかたちの欲望や他国に対する恐怖心への対抗などであったが、それでも、世界のすべての人が平和を希求し、さまざまな手法で模索し続けてきたのもまた事実だ。この現実の矛盾する構造は、二一世紀の現在も基本的に変わっていない。本書は、過去から現在まで、人類がどのように平和に取り組み、それがどう成功し、どう失敗してきたかをテーマごとに考察し、その中から現代の国際政治がいかにして平和の確立を図るべきか、ヒントを探ろうとする試みである。
目次
「念仏では平和は維持できない」
軍事と政策の平和史
領土と国境の平和史
諜報と工作の平和史
人望と交渉の平和史
お詫びと貢ぎ物の平和史
信仰と憎悪の平和史
理解と無理解の平和史
開戦と終戦の平和史
理論と実践の平和史
国際機構と協力の世界史
日本は「平和」にどう貢献するのか
著者等紹介
吹浦忠正[フキウラタダマサ]
1941年、秋田市生まれ。早稲田大学政経学部政治学科卒。同大学院政治学研究科修了。現在、東京財団常務理事。「難民を助ける会」特別顧問、(社)「協力隊を育てる会」常任理事、安全保障問題研究会委員・事務局長、東洋英和女学院大学大学院非常勤講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
6
対人地雷で「2002年には11700人の死傷者を出しているとのこと。そのうち、軍関係者は15%に過ぎず、大半の被害者は非戦闘員である民間人だったという。この報告書は死傷者を、①チェチェン共和国(ロシア)の5695人、②アフガニスタンの1286人、③カンボジアの834人、④コロンビアの530人、⑤イラクの457人の順に列挙している。これまで筆頭級だったアンゴラは長年の内戦が終結したことからこの中には入らなかった」すなわち、ロシアはある意味ずっと内戦が続いているということだ。2017/02/19
kawa
6
プロローグで紹介される、司馬遼太郎氏の「平和を維持するためには、人脂のべとつくような手練手管が要る。」と、日本人に多いとされる「平和念仏主義」〜平和念仏を唱えていればすべて解決、念仏を唱えない者はすべて戦争屋だ〜の単純なレッテル貼りに対する警鐘は、的を得ていて印象的。残念なことだが、未だにそういう傾向が強いように思う。古今東西の平和への手練手管が紹介されるが、その内容にインパクトを感じられないのが新書版の限界かな。2016/03/10
乱読家 護る会支持!
3
「原爆の悲惨さを訴えて」 「核拡散防止条約で新たな国の核保有を認めない」 「既存の核保有国の核軍縮の推進」 「戦時中に日本が起こした非人道行為を反省」などなど、、、 2004年に出版された本なので、当時の平和志向を表していて、現在から見ればまだまだ平和ボケのリベラル思考から抜け出ていないように見える。 この後、アメリカの弱体化、北朝鮮の核兵器のミサイル開発、中国共産党の軍備拡大が明確になり、日本が海外の軍事的脅威にさらされるようになり、多くの日本人が目覚めていったように思う。2021/02/25
本命@ふまにたす
2
「平和」に関する様々な事柄について、主に現実主義的な立場から論じる。著者の立場については意見が分かれそうだが、世界の歴史における様々な事柄が引かれていて参考になる。2022/03/17
おらひらお
2
2004年初版。様々なケースを挙げ戦争ではない状態(つまり平和)のあり方を概観する。やはり国内だけでの議論では何も進展しないことを再認識させる一冊ですね。2016/02/06