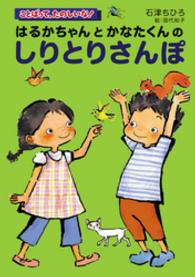内容説明
「高座の上で戦うことは大いに結構なことだと思います。ただ、現在の落語界は、その前の精神戦でクタクタになっている人が、あまりにも多過ぎるのです。私が前座の頃は、いい意味での仲間意識がもっとあったような気がします」ギシギシと音をたて続けている平成の落語界。不安・嫉妬・絶望と戦い続ける噺家たちの実像に迫る。
目次
第1章 新人の頃(兄弟子;初高座 ほか)
第2章 落語界改造計画(真打昇進披露;弟子入り志願者 ほか)
第3章 二十一世紀の落語(笑いについて;セルフプロデュースについて ほか)
第4章 十年後の落語界(小朝が選ぶ十年先のメンバー;新作派の秘密兵器たち ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
奈良 楓
0
組織は落語でもサラリーマンでも変わらないな、と思いました。2013/07/21
おさんぽねこさん
0
随分前に読んだのだった。「大銀座落語祭」のあたりだから何年前かな? 新作/古典ともに良い形で刺激し合って生き残って行けばよいのじゃ。 生き残って行く力のある噺は語り継がれ古典になるのだから。
namng
0
西暦2000年に発行された新書本。来る21世紀の落語界への小朝師の提言をまとめている。 いずれもまっとうな提言で、例えば昇太師らのSWA(創作話芸アソシエーション)での活動などは、この本での小朝師の提言が土台に有るのではないか。 軽く読めたが、読み応えが有った。2011/11/09
4k
0
あっという間に読めるが内容は深い。ここから銀座落語祭や正蔵三平襲名へと繋がるのだから。2009/07/01
朱音
0
父親が図書館から借りてきていたもの。芸譚とか好きなんですよね父は。いつもは歌舞伎なのにな、と思いながら読んでみたんだけど、結構これが面白かった。芸譚とはちょっと違っていて、暴露的でもなくって。まあつまりは、寄席人気がいまいちな今、落語界の未来はどうなる?っていうことなんだけど。実際私も最近は漫才は見ても落語見ませんね。文珍さんとか好きなんだけど。2002/07/28