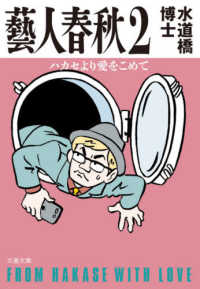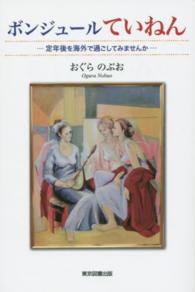内容説明
異国の地で仏道修行に励むこと二十有余年。黄衣をまとい、ブッダの道を歩む著者がいる。ブッダの時代のエッセンスが今も息づく山寺の修行生活。「癒し」を求め、著者のもとを訪れる日本人たちと紡いだ物語。それが今、あなたへの「智慧と慈しみ」のメッセージに―。
目次
第1章 出家の経緯と開発僧(最初の仏縁;宮沢賢治の言葉に触れて ほか)
第2章 タイのテーラワーダ仏教(山寺の朝;タイ仏教・タイの寺 ほか)
第3章 気づきの瞑想(ブッダの教えた瞑想;タイの代表的な四つの瞑想法 ほか)
第4章 一期一会の出会い(人間関係の問題から思考のパターンに気づく;カンポンさんとの対話を通して学び、癒される日本人たち ほか)
第5章 「気づきの瞑想」を生きるキーワード(苦しみからの解放を得る;苦しみのからくり―みずからの困難をよき縁とする ほか)
著者等紹介
プラユキ・ナラテボー[プラユキナラテボー][Phrayuki Naradevo]
1962年生まれ。タイ・スカトー寺副住職。上智大学卒業後、タイのチュラロンコン大学大学院に留学。研究テーマは農村開発におけるタイ僧侶の役割。1988年、瞑想指導者として有名なルアンポー・カムキアン師のもとで出家。以後、村人のために物心両面の幸せを目指す開発僧として活動する一方、日本とタイを結ぶ架け橋としても活躍。また、在日タイ人の支援活動にも携わっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
西
7
自分の気持ちにどれだけ気付けるか。不機嫌になったのは何が本当の原因か、それならどういう方法でそれから逃れることができるか、解決できるかを考えること。気付いてみると本当にくだらないことで不機嫌になってしまっていることが多いなと思う。瞑想はなかなかうまくいかないので行えていないけど、今の自分の気持ちに気付くことは、以前よりできるようになったと思う2023/04/16
isao_key
6
タイ・チャイヤプーム県スカトー寺で25年以上修行を行っている著者の体験談とメッセージ。読みながら同じタイに住んでいてよく理解できる部分と、改めて気づかされた部分があった。同じスカトー寺に住む、在家信徒のカンポンさんの言葉が胸を打つ。「相手からの愛を待つのではなく、自分から人を愛すると、まず自分の心の中に愛が生まれて満たされる。その温かい愛の気持ちを花のような言葉で包んで相手に贈ってあげる」また朝の托鉢で子どもが敬虔な様子で食事を捧げ合掌する姿は、親が強制したのではなく、自ら行っているので、愛らしく美しい。2014/12/13
kera1019
6
「背中の重荷に気づけ。荷を降ろせ。そうすれば誰でもが、軽やかに、自由に、そして幸せに生きられる。」その答えが「気づきの瞑想」であり生活即修行である。自分が如何にとらわれてるかわかっていてもそこから離れることが中々出来ない。托鉢や説法、宗教的上下関係などタイでは原始仏教が生活に根付いてる事がよくわかる。「まず、みずからを拠りどころとせよ」と今ここに気づいていること、気づきの瞑想によって、今ここに立ち戻る術を身につけて洞察が生まれ、因果の理法を観るに至った時、心の質を高め、苦しみのパターンから解放される。2014/07/05
ANDY
2
私もカンポンさんのような心を持ちたい。2014/10/21
くらーく
1
タイと日本で、瞑想の仕方が変化しているのかな。どうも、日本に来ると先鋭化すると言うか純化するというか。中庸を許さないのかな、なんて思いながら読む。同世代の著者の生き方も、羨ましいような、反発を覚えるような。 一読しておいて、ためになる本。少し肩の荷を降ろして、リラックスしましょうかね。2015/06/27