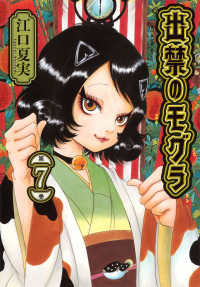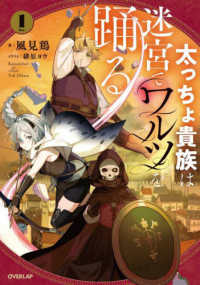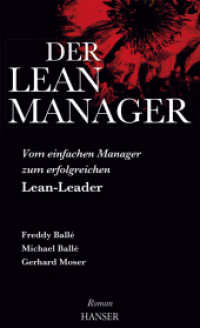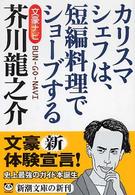出版社内容情報
日本でも注目されている「ヨーロッパ言語共通参照枠」(CEFR)の全体像を理解し、授業で生かすためのヒントが学べる。「Can―doリスト」やELP(ヨーロッパ言語ポートフォリオ)の活用など幅広いテーマを扱った。
CEFRの理解、導入、実践のための一冊
近年、日本国内でも注目を集めている「ヨーロッパ言語共通参照枠」(CEFR)の全体像を理解し、授業で生かすためのヒントが学べる。CEFRが教育現場でどのように取り入れられてきたかについて、ヨーロッパでの先進的な事例を挙げながら説明し、CEFR導入の意義のほか、実践上の問題点や課題を客観的に述べる。「Can-doリスト」やELP(ヨーロッパ言語ポートフォリオ)の活用、自己評価、学習者の自立、シラバス・教材・試験との関連づけ、教員教育への導入といった幅広いテーマを扱った。
第1章 背景
1. CEFRの背景
2. なぜCEFRは重要なのか
第2章 学習者の学びを支える : ポートフォリオ、自己評価、方略の指導
1. ヨーロッパ言語ポートフォリオ
2. CEFRを用いて学び方を学ぶ
第3章 コース設計と教員教育におけるCEFR
1. CEFRと中等学校用シラバス
2. 教員養成と現職教員研修におけるCEFR
第4章 学習者ができることを明らかにすること
1. 診断型テストを通じて言語学習を促進するためのCEFRの利用
2. 評価、試験、講座をCEFRに関連づけること
第5章 シラバスと教材の設計
1. アイルランド初等学校における事例研究 : 転入生徒に対するESLカリキュラム開発のためのCEFRの活用
2. ブリティッシュ・カウンシル・ミラノにおける事例研究 :10代の生徒を対象とした英語コース開発のためのCEFRの活用
3. グロスターシャー大学における事例研究 : 成人対象の英語コース開発のためのCEFRの活用
【著者紹介】
キース・モロウ (Keith Morrow) ELT Journal 編集長
和田 稔 (わだ みのる) 明海大学名誉教授
高田智子 (たかだ ともこ) 明海大学准教授
緑川日出子 (みどりかわ ひでこ) 昭和女子大学非常勤講師
柳瀬和明 (やなせ かずあき) 日本英語検定協会制作部アドバイザー
齋藤嘉則 (さいとう よしのり) 文部科学省初等中等教育局教科書調査官
内容説明
近年、日本国内でも注目を集めている「ヨーロッパ言語共通参照枠」(CEFR)の全体像を理解し、授業で生かすためのヒントを学ぶことができる。CEFRが教育現場でどのように取り入れられているかについて、ヨーロッパでの先進的な事例を挙げながら説明し、その意義や実践上の課題を客観的に述べる。「Can‐doリスト」やELP(ヨーロッパ言語ポートフォリオ)、自己評価、学習者の自律、シラバス・教材・試験との関連づけ等、幅広いテーマを扱った。
目次
第1章 背景(CEFRの背景;なぜCEFRは重要なのか)
第2章 学習者の学びを支える:ポートフォリオ、自己評価、方略の指導(ヨーロッパ言語ポートフォリオ;CEFRを用いて学び方を学ぶ)
第3章 コース設計と教員教育におけるCEFR(CEFRと中等学校用シラバス;教員養成と現職教員研修におけるCEFR)
第4章 学習者ができることを明らかにすること(診断型テストを通じて言語学習を促進するためのCEFRの利用;評価、試験、講座をCEFRに関連づけること)
第5章 シラバスと教材の設計(アイルランド初等学校における事例研究:転入生徒に対するESLカリキュラム開発のためのCEFRの活用;ブリティッシュ・カウンシル・ミラノにおける事例研究:10代の生徒を対象とした英語コース開発のためのCEFRの活用;グロスターシャー大学における事例研究:成人対象の英語コース開発のためのCEFRの活用(ピアズ・ウォール))
著者等紹介
モロウ,キース[モロウ,キース] [Morrow,Keith]
ELT Journal編集長
和田稔[ワダミノル]
1938年生まれ。東京教育大学文学部英米語学科卒業。3校の千葉県立高等学校で英語を教えたあと、千葉県教育センター研修主事、千葉県教育委員会外国語教育担当指導主事を経て、文部省(当時)初等中等教育局外国語教育担当教科調査官の仕事に当たる。その後、明海大学外国語学部および同大学応用言語学研究科で教鞭をとり、2008年3月に定年退職。現在、明海大学名誉教授
高田智子[タカダトモコ]
お茶の水女子大学文教育学部卒業。ボストン大学M.Ed.(TESOL)、ニューヨーク大学Ph.D.(TESOL)取得。学習院女子中・高等科教諭を経て、明海大学外国語学部准教授。文部科学省「外国語教育における「CAN‐DOリスト」の形での学習到達目標設定に関する検討会議」委員
緑川日出子[ミドリカワヒデコ]
テンプル大学教育学部修士。公立高等学校の教諭、昭和女子大学人間文化学部教授、同大学大学院文学研究科教授を経て、同大学英語コミュニケーション学科非常勤講師。英語授業研究学会理事、文部省指導者講座講師、文部省学習指導要領改訂協力者会議委員などを歴任。専門は英語教授法、教室での第二言語習得、英語教育。CEFRの理念と教育実践の日本への応用可能性に関する研究に取り組んでいる
柳瀬和明[ヤナセカズアキ]
都立高校での教員を経て、公益財団法人日本英語検定協会制作部アドバイザー。オーストラリアの各種教育機関で日本語教育に従事した経験を持つ。英検の問題作成・分析、各種英語試験や英語学習に関する調査研究などに従事
齋藤嘉則[サイトウヨシノリ]
1958年生まれ。宮城教育大学教育学部卒業後、宮城県公立中学校教諭、現職のまま内地留学にて宮城教育大学大学院英語教育専修修了(教育学修士)。仙台市教育局学校教育部教育センター指導主事、仙台市立中学校教頭、宮城教育大学教職大学院准教授を経て、文部科学省初等中等教育局教科書調査官(外国語)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。