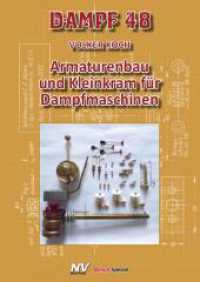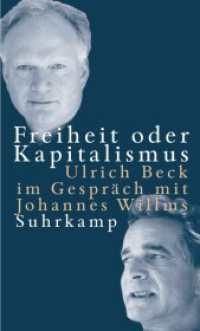出版社内容情報
統語との共通点(規則性)と相違点(語彙性)という語形成の持つ二面性を軸に、英語と日本語の言語事実を対象として、異なるレベルで扱うべき問題、質的相違が関連する問題など、多様な語形成プロセスを考察する。
第I部 極性
はじめに
第1章 語形成とレキシコン
1.1 はじめに
1.2 語の構造と語形成
1.3 語という単位
1.4 メンタルレキシコン
1.5 語の生産性と規則性
1.6 文法における語形成の位置づけ
第2章 語彙表示レベルと語形成
2.1 語彙的統語表示と語彙的意味表示
2.2 項構造と語形成
2.2.1 項構造と接辞付加/2.2.2 項構造と複合語の形成
2.3 意味的語彙表示レベルと語形成
2.3.1 語彙概念構造に基づく派生動詞の形成/2.3.2 語彙概念構造と接頭辞付加
2.4 まとめ
第3章 複数のレベルにまたがる語形成
3.1 英語の名詞化
3.1.1 さまざまな名詞化/3.1.2 複雑事象名詞と項構造/3.1.3 -ingによる名詞化:規則による複雑事象名詞/3.1.4 LCSと結果名詞/3.1.5 単純事象名詞とLCS
3.2日本語の動詞の名詞化
3.2.1 動詞連用形の名詞用法/3.2.2 動詞連用形からの転換名詞と項構造/3.2.3 接辞付加による名詞化
3.3 日本語の動詞由来複合語の形成
3.3.1 内項を含む動詞由来複合語/3.3.2 付加詞を含む動詞由来複合語/3.3.3 付加詞+動詞の複合とLCS/3.3.4 付加詞の複合と複雑述語形成/3.3.5 2種類の動詞由来複合語の音韻的3 使役化接辞の脳内メカニズム
4.4 まとめ
第5章 まとめ参考文献/索引
内容説明
語の仕組みと語形成は、人間の無限の言語生成能力の一翼を担っており、言語研究において極めて重要な意味合いをもつ分野である。「語」はそれ固有の特異な情報とともに、形と意味が記憶されている(=語彙性)と同時に、活用や派生といった、さまざまな語形成規則によって変化し、その形成過程や内部構造に規則性をもつという点で、二面性をもっている。本書は、この語という単位のもつ二面性を、英語と日本語のさまざまな語形成現象を取り上げながら、詳しく論じたものである。
目次
第1章 語形成とレキシコン(語の構造と語形成;語という単位 ほか)
第2章 語彙表示レベルと語形成(語彙的統語表示と語彙的意味表示;項構造と語形成 ほか)
第3章 複数のレベルにまたがる語形成(英語の名詞化;日本語の動詞の名詞化 ほか)
第4章 語形成の心的メカニズム(屈折接辞の生産性:規則と連想記憶;名詞化とDM仮説 ほか)
第5章 まとめ
著者等紹介
伊藤たかね[イトウタカネ]
1955年大分県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学(1984)。現在、東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻教授
杉岡洋子[スギオカヨウコ]
1954年兵庫県生まれ。シカゴ大学大学院博士課程修了。Ph.D.(言語学)。現在、慶応義塾大学教授
原口庄輔[ハラグチショウスケ]
1943年生まれ。明海大学外国語学部教授
中島平三[ナカジマヘイゾウ]
1946年生まれ。東京都立大学教授
中村捷[ナカムラマサル]
1945年生まれ。東北大学大学院文学研究科教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
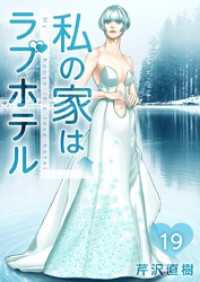
- 電子書籍
- 私の家はラブホテル 19巻 Comic…