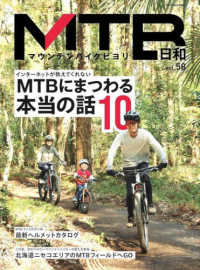出版社内容情報
Ⅰ 山岳
山と私
絵に添えて
1 絵に添えて
2 モリス氏の話
ヒマラヤ登攀史 1 初期の旅行者並びに登山者
2 ガルワール
3 シッキム
北千島ポロモシリ島
新雪の富士にて
巴里便り
1 巴里便り
2 メイジュを眺めて
初夏の谷川に想う
キリマンジャロの二つの頂上
マッキンレー 1960年―西南稜の登攀
登山会が今日問題にすべきこと
大学山岳部とOBについて
諸君は遭難にさらされている
ベントのピッケル
Ⅱ 雪氷
雪と私
北千島学術調査隊建築調査報告
建物周囲の吹溜り積雪状況に関する模型実験
積雪学への提案
1 概説
2 建築学を中心に
流雪溝の例について
積雪地方の都市計画について
雪国及び寒冷地の生活と建築
日本の南極基地ができるまで
入広瀬村のこと
雪国の都市と建築について
豪雪は日本の資源
Ⅲ 山岳建築
劔山荘の計画に想いて
山と建築
応酬の山小舎
世界の山小屋物語
1 アラスカ・ハイウェーの山小屋
2 キリマンジャロの山小屋
3 スイス・アルプスの山小屋
4 チロル山地の山小屋
一連の山岳建築作品群
安達太良山小屋
大阪経済大学山小屋
涸沢ヒュッテ
黒沢池ヒュッテ
富山県立立山荘
立山山岳ホテル
日本登山学校・山岳会館
早大山岳アルコウ会ヒュッテ
東海テレビ湯の山「山の家」
野沢温泉ロッジ
ニューフサジ
ヒュッテアルプス
大観峰駅
山田牧場ヒュッテ
解説・後記
解説 ....................松崎義徳
後記 ..................村田真 山中公一 【目次】
Ⅰ 山岳
山と私
絵に添えて
1 絵に添えて
2 モリス氏の話
ヒマラヤ登攀史 1 初期の旅行者並びに登山者
2 ガルワール
3 シッキム
北千島ポロモシリ島
新雪の富士にて
巴里便り
1 巴里便り
2 メイジュを眺めて
初夏の谷川に想う
キリマンジャロの二つの頂上
マッキンレー 1960年―西南稜の登攀
登山会が今日問題にすべきこと
大学山岳部とOBについて
諸君は遭難にさらされている
ベントのピッケル
Ⅱ 雪氷
雪と私
北千島学術調査隊建築調査報告
建物周囲の吹溜り積雪状況に関する模型実験
積雪学への提案
1 概説
2 建築学を中心に
流雪溝の例について
積雪地方の都市計画について
雪国及び寒冷地の生活と建築
日本の南極基地ができるまで
入広瀬村のこと
雪国の都市と建築について
豪雪は日本の資源
Ⅲ 山岳建築
劔山荘の計画に想いて
山と建築
応酬の山小舎
世界の山小屋物語
1 アラスカ・ハイウェーの山小屋
2 キリマンジャロの山小屋
3 スイス・アルプスの山小屋
4 チロル山地の山小屋
一連の山岳建築作品群
安達太良山小屋
大阪経済大学山小屋
涸沢ヒュッテ
黒沢池ヒュッテ
富山県立立山荘
立山山岳ホテル
日本登山学校・山岳会館
早大山岳アルコウ会ヒュッテ
東海テレビ湯の山「山の家」
野沢温泉ロッジ
ニューフサジ
ヒュッテアルプス
大観峰駅
山田牧場ヒュッテ
解説・後記
解説 ....................松崎義徳
後記 ..................村田真 山中公一
【目次】
Ⅰ 山岳
山と私
絵に添えて
1 絵に添えて
2 モリス氏の話
ヒマラヤ登攀史 1 初期の旅行者並びに登山者
2 ガルワール
3 シッキム
北千島ポロモシリ島
新雪の富士にて
巴里便り
1 巴里便り
2 メイジュを眺めて
初夏の谷川に想う
キリマンジャロの二つの頂上
マッキンレー 1960年―西南稜の登攀
登山会が今日問題にすべきこと
大学山岳部とOBについて
諸君は遭難にさらされている
ベントのピッケル
Ⅱ 雪氷
雪と私
北千島学術調査隊建築調査報告
建物周囲の吹溜り積雪状況に関する模型実験
積雪学への提案
1 概説
2 建築学を中心に
流雪溝の例について
積雪地方の都市計画について
雪国及び寒冷地の生活と建築
日本の南極基地ができるまで
入広瀬村のこと
雪国の都市と建築について
豪雪は日本の資源
Ⅲ 山岳建築
劔山荘の計画に想いて
山と建築
応酬の山小舎
世界の山小屋物語
1 アラスカ・ハイウェーの山小屋
2 キリマンジャロの山小屋
3 スイス・アルプスの山小屋
4 チロル山地の山小屋
一連の山岳建築作品群
安達太良山小屋
大阪経済大学山小屋
涸沢ヒュッテ
黒沢池ヒュッテ
富山県立立山荘
立山山岳ホテル
日本登山学校・山岳会館
早大山岳アルコウ会ヒュッテ
東海テレビ湯の山「山の家」
野沢温泉ロッジ
ニューフサジ
ヒュッテアルプス
大観峰駅
山田牧場ヒュッテ
解説・後記
解説 ....................松崎義徳
後記 ..................村田真 山中公一
内容説明
「登山という行為そのものが、本来は『それ』から出発したものだと私は考える。…『それ』は喜怒哀楽の波にもまれて終わる短い人生に,一つでも二つでも喜びや楽しいことの方を追加することなのだ。忘れられたり、知られずにいたものを発見して皆の宝とすることなのだ」(「マッキンレー1960年」) あらゆる世界に、未登の頂を発見せんとした建築家吉阪にとって、極地,豪雪地、山岳地の住居・都市像は、正に皆の宝とすべき未登の頂であった。胎動間もない日本の雪氷学を背負い,山小屋の岩肌にきざんで一歩一歩昇って行った吉阪。どこでもいい。吉阪の生み出した山小屋目指して登ってみよ。激しい風雪と闘うためにあらゆる虚飾を剥ぎ取った原型としての砦が、暖かく迎えてくれるはずだ。