出版社内容情報
Ⅰ 造形との出会い
プレリュード―私はなぜコンクリートにこだわるのだろう
住居デザイン論
Ⅱ ある住居―自邸
パリからの手紙
『ある住居・一つの試み』
人工土地の家
Ⅲ 設計というドラマ
住宅を設計するとは
夙川の家―浦邸
書簡=設計者から施主浦氏へ
正方形を二つ組み合わせる
夙川の家
設計表現の合理化―図面における新しい試み
ヴィラ・クゥクゥ―近藤邸
アパート病対策を思いつつ
2+1=2
ヴィラ・クゥクゥ
コンクリートで住宅を作る
Ⅳ 形の意味を求めて
形の意味を求めて―壁と柱と床の発生
外部の内部の部分
プランと生活
練馬の家―及川邸
国分寺の家―十河邸
豪徳寺の家―丸山邸
茅ケ崎の家―竹田邸
鵠沼の家―赤星邸
成城の家―樋口邸
葉山の家―三沢邸
私の住宅論
Ⅴ わが住いの変遷史
わが住いの変遷史
誕生の前後
幼年期の頃
少年期頃のテリトリー
ジュネーヴのお屋敷で
下宿時代
1945年5月25日焼失
同居から単居まで
もう一つの経験
「薩摩会館」での二年間
アルゼンチンでの二年間
百人町での改装と拡大
ボストンでの転機
自邸・その後
自邸
実験家屋に住む
春の一番のり
解説・後記
解説.........................植田實
後記.........................斎藤祐子 【目次】
Ⅰ 造形との出会い
プレリュード―私はなぜコンクリートにこだわるのだろう
住居デザイン論
Ⅱ ある住居―自邸
パリからの手紙
『ある住居・一つの試み』
人工土地の家
Ⅲ 設計というドラマ
住宅を設計するとは
夙川の家―浦邸
書簡=設計者から施主浦氏へ
正方形を二つ組み合わせる
夙川の家
設計表現の合理化―図面における新しい試み
ヴィラ・クゥクゥ―近藤邸
アパート病対策を思いつつ
2+1=2
ヴィラ・クゥクゥ
コンクリートで住宅を作る
Ⅳ 形の意味を求めて
形の意味を求めて―壁と柱と床の発生
外部の内部の部分
プランと生活
練馬の家―及川邸
国分寺の家―十河邸
豪徳寺の家―丸山邸
茅ケ崎の家―竹田邸
鵠沼の家―赤星邸
成城の家―樋口邸
葉山の家―三沢邸
私の住宅論
Ⅴ わが住いの変遷史
わが住いの変遷史
誕生の前後
幼年期の頃
少年期頃のテリトリー
ジュネーヴのお屋敷で
下宿時代
1945年5月25日焼失
同居から単居まで
もう一つの経験
「薩摩会館」での二年間
アルゼンチンでの二年間
百人町での改装と拡大
ボストンでの転機
自邸・その後
自邸
実験家屋に住む
春の一番のり
解説・後記
解説.........................植田實
後記.........................斎藤祐子
【目次】
Ⅰ 造形との出会い
プレリュード―私はなぜコンクリートにこだわるのだろう
住居デザイン論
Ⅱ ある住居―自邸
パリからの手紙
『ある住居・一つの試み』
人工土地の家
Ⅲ 設計というドラマ
住宅を設計するとは
夙川の家―浦邸
書簡=設計者から施主浦氏へ
正方形を二つ組み合わせる
夙川の家
設計表現の合理化―図面における新しい試み
ヴィラ・クゥクゥ―近藤邸
アパート病対策を思いつつ
2+1=2
ヴィラ・クゥクゥ
コンクリートで住宅を作る
Ⅳ 形の意味を求めて
形の意味を求めて―壁と柱と床の発生
外部の内部の部分
プランと生活
練馬の家―及川邸
国分寺の家―十河邸
豪徳寺の家―丸山邸
茅ケ崎の家―竹田邸
鵠沼の家―赤星邸
成城の家―樋口邸
葉山の家―三沢邸
私の住宅論
Ⅴ わが住いの変遷史
わが住いの変遷史
誕生の前後
幼年期の頃
少年期頃のテリトリー
ジュネーヴのお屋敷で
下宿時代
1945年5月25日焼失
同居から単居まで
もう一つの経験
「薩摩会館」での二年間
アルゼンチンでの二年間
百人町での改装と拡大
ボストンでの転機
自邸・その後
自邸
実験家屋に住む
春の一番のり
解説・後記
解説.........................植田實
後記.........................斎藤祐子
内容説明
本巻は30年に及ぶ吉阪の住宅設計と住宅設計論の足跡である。第1巻~第3巻と併せ読むことによって、読者は吉阪の住居、住生活、住宅設計の発見、観察、理論、実践という、大胆かつ細心な旅を辿ることができるだろう。
目次
1 造形との出会い
2 ある住居―自邸
3 設計というドラマ
4 形の意味を求めて
5 わが住まいの変遷史
-

- 電子書籍
- 青野くんに触りたいから死にたい 分冊版…
-

- 電子書籍
- リコーダーとランドセル【分冊版】 28…
-
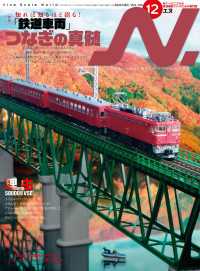
- 電子書籍
- N. (エヌ) 2023年12月号 〈…
-

- 電子書籍
- 料理つくらず恋せよ乙女~上司と私のおい…
-
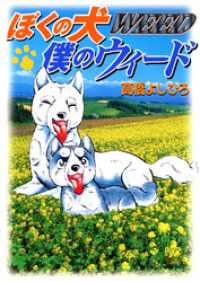
- 電子書籍
- ぼくの犬僕のウィード ニチブンコミックス



