出版社内容情報
私たちには、怒りや憎しみ、激しい愛など中から溢れ出そうとするものが存在している。ときにそれは、他人を傷つけてしまう力、つまり暴力を発揮する。一方、このような溢れ出そうとするものを、私たちはほとんど外側から痕跡が見えないほど見事に抑え切ってしまう。このような「私」はどのようにできたのだろうか。
本書は『文明化の過程』や『宮廷社会』などの著作で知られるノルベルト・エリアスの研究を通し、人が感情の発露を抑制するようになる過程や、逆に暴力がより先鋭化してしまう現象をドイツやイギリスなどの歴史的経緯から、探る。
【目次】
序章 暴力を問うための場所
1 ポーランドのふたつの町
2 ノルベルト・エリアスとはだれか
3 暴力に対する態度
第1章 「文明化された私」への問い―『文明化の過程』
1 「自己意識」から「ふるまい」へ―問いを準備する作業
2 「自己抑制」する人間―「礼儀作法」の歴史社会学
3 相互依存・国家・階級―「社会発生」の論理
4 「暴力」のある自画像―残された課題
第2章 個人の解体・社会の解体―方法論的考察
1 「個人」対「社会」の構図―『諸個人からなる社会』
2 「過程」と「関係態」の社会学―ホモ・クラウススへの批判
第3章 「脱文明化」と階級のハビトゥス―戦後の共同研究
1 エリアスの戦後―ふたつの「現実」
2 「インフォーマル化」の過程―オランダでの研究
3 スポーツ・暴力・労働者階級―イギリスでの研究
第4章 われわれの「理想」と「暴力」―『ドイツ人論』
1 ドイツ市民層のハビトゥス―「決闘を許された社会」
2 「われわれ理想」とその挫折―ヒューマニズムからナショナリズムへ
3 「暴力」の悪循環過程―ワイマール時代のテロリズム
4 世代・スティグマ・もうひとつの理想―戦後ドイツのテロリズム
第5章 「知識」という迂回路―知識とシンボルの社会学の構想
1 距離化・制御・社会の科学―『参加と距離化』
2 過程としての知識・過程としての人類―『シンボルの理論』
注
おわりに
参考文献
索引
内容説明
なぜ人は暴力をふるうのか?なぜ人は暴力を抑えるのか?「文明化」の帰結を問い続けた社会学者ノルベルト・エリアス。その全体像を解明する。
目次
序章 暴力を問うための場所
第1章 「文明化された私」への問い―『文明化の過程』
第2章 個人の解体・社会の解体―方法論的考察
第3章 「脱文明化」と階級のハビトゥス―戦後の共同研究
第4章 われわれの「理想」と「暴力」―『ドイツ人論』
第5章 「知識」という迂回路―知識とシンボルの社会学の構想
著者等紹介
奥村隆[オクムラタカシ]
1961年徳島県に生まれる。1984年東京大学文学部卒業。1990年東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。東京大学文学部助手、千葉大学文学部講師を経て、現在千葉大学文学部助教授。専攻社会学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モルテン
soto
-

- 電子書籍
- 治癒魔法の間違った使い方 ~戦場を駆け…
-
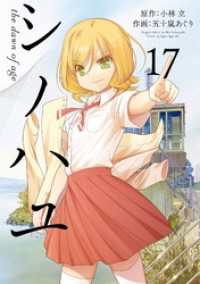
- 電子書籍
- シノハユ the dawn of ag…
-
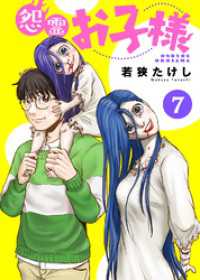
- 電子書籍
- 怨霊お子様(7) COMICアンブル
-

- 電子書籍
- 男だけど死神姫の嫁になりました(仮)【…
-
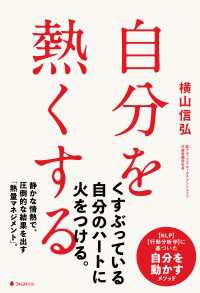
- 電子書籍
- 自分を熱くする




