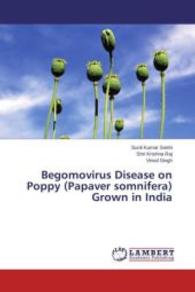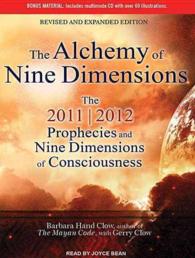出版社内容情報
「公法史」という学問領域の存立意義を世界に知らしめた名著『ドイツ公法史』全4巻。著者自身がその精髄をまとめた入門書。
法治国家、権力分立、国民主権……ドイツ人は国家についてどう思索してきたのか。「公法についての学問史」という視点の下、神聖ローマ帝国からヴァイマル時代を経て東西分断・再統一まで、数世紀にわたる憲法――国のかたち――を巡る学問の歴史を、行政法や社会保障、国際法・EU法などと連携させつつ描く、ドイツ公法史の金字塔。
【原著】Michael Stolleis, Offentliches Recht in Deutschland:Eine Einfuhrung in seine Geschichte, 16. - 21. Jahrhundert(C・H・Beck, 2014)
内容説明
「公法についての学問史」という視点の下、神聖ローマ帝国からヴァイマル時代を経て東西分断・再統一まで、600年にわたる憲法―国のかたち―を巡る学問の歴史を、行政法や社会保障、国際法・EU法などと連携させつつ描く、ドイツ公法史の金字塔。
目次
第1章 イントロダクション、対象、方法
第2章 ローマ法からの解放―国制法の法源論の変遷
第3章 揺籃期公法学の諸潮流
第4章 帝国公法学、自然法、国際法、「良きポリツァイ」
第5章 革命と王政復古の間の公法
第6章 パウル教会
第7章 帝国国法学
第8章 初期産業社会の国家における行政法
第9章 ヴァイマル憲法の下での国法学・行政法学
第10章 方法論争と一般国家学の諸流派
第11章 ヴァイマル共和国時代の行政法
第12章 ナチス国家とその公法
第13章 ドイツの法的地位、再建、二つの国家
第14章 新しい「価値秩序」と法治国家の再建
第15章 社会国家・介入国家としてのドイツ連邦共和国
第16章 ドイツ民主共和国における国法・国際法・行政法
第17章 ヨーロッパ法・国際法
第18章 再統一
第19章 グローバル化と国家の将来
第20章 終わりに
著者等紹介
シュトライス,ミヒャエル[シュトライス,ミヒャエル] [Stolleis,Michael]
1941年生まれ。2021年逝去。法学者。フランクフルト大学法学部教授(1975~2006年)、マックス・プランク・ヨーロッパ法史研究所所長(1992~2009年)。ルンド(スウェーデン)、トゥールーズ、パドヴァ、ヘルシンキ各大学名誉博士。バルザン章、プール・ド・メリット勲章等
福岡安都子[フクオカアツコ]
1977年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授。東京大学大学院法学政治学研究科助手を経て、現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえぽん
馬咲
フクロウ
261bei