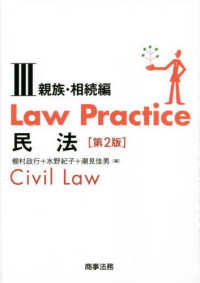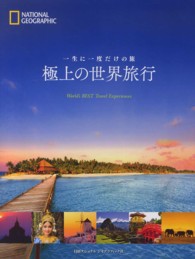出版社内容情報
人間形成における経験の意味とは何か。人が他者、異文化、異世界など様々な外部と出会う中、自已と他者が織り成す、物語の構築と解体のプロセスを問い直す。
人が生きるということは、他者との間に何らかの物語を構築し、それを共有したり、破壊させたり、綻びを繕ったりしつつ物語を編み直し続ける営みである。経験、関係、空間などのキーワードをもとに、人間という生のかたちの変成の問題を人間学的に考察し、教育や子育ての問題を、変成し合うダイナミズムの中で、巨視的に捉え論じる。
[関連書] 同著者 『文化変容のなかの子ども』 (東信堂)
はしがき
序 章 経験のメタモルフォーゼ――<自己変成>の教育人間学
1 流動し変成する生命
2 相互変成体としての生
3 「生きられた世界」とその変成
4 異邦と故郷
5 越境と他者
6 経験のメタモルフォーゼ
第一章 変成される世界――秩序を無化する経験
1 諸刃の剣としての経験――日常とカオスの裂け目
2 否定の経験
3 根源的な生活世界の経験
4 変成される世界
第二章 人間形成における「関係」の解読――経験・ミメーシス・他者
1 <教師‐生徒>関係というアポリア
2 「生きられた時間」とライフサイクル――台形型と円環型
3 構成された社会的世界への参入
4 経験とミメーシス
5 迷路に迷い込む経験
6 異界と遊ぶ子ども
7 人間形成における「関係」の多次元性――子どもと老人をつなぐ物語
第三章 受苦的経験の人間学
1 負担軽減としての経験
2 経験の原初的構造
3 経験と他者
4 受苦的経験と臨床知の感得
第四章 脱中心化運動としての教育人間学
――Ch・ヴルフの歴史的教育人間学の地平
1 「教える‐学ぶ」という関係図式
2 脱中心化運動としての教育人間学
3 教育人間学の多種多様な展開
4 歴史的教育人間学の地平
5 教育人間学の今後の展開
第五章 「発達」からメタモルフォーゼへ
1 「発達」というまなざし
2 世界の変成
3 「発達」からメタモルフォーゼへ
第六章 異化作用としての経験
1 経験のパラドックス
2 構築された「現実」の流動性
3 homo patiens
4 「現実」の動的な編み直し
第七章 子どもが生きられる空間
1 機能化された都市空間
2 子どもが経験する空間
3 子どもが生きられる空間
終 章 子どもの自己形成空間
1 子どもの自己形成空間
2 情報・消費社会と子ども
3 自己決定主義の陥穽
4 学校、家庭、地域をすり抜ける子ども
初出一覧
あとがき
参考文献一覧
事項索引
人名索引
内容説明
人間形成における経験の意味とは何か。人が様々な外部と出会う中、自己と他者が織り成す物語の構築と解体のプロセスを問い直す。
目次
序章 経験のメタモルフォーゼ―“自己変成”の教育人間学
第1章 変成される世界―秩序を無化する経験
第2章 人間形成における「関係」の解読―経験・ミメーシス・他者
第3章 受苦的経験の人間学
第4章 脱中心化運動としての教育人間学―Ch・ヴルフの歴史的教育人間学の地平
第5章 「発達」からメタモルフォーゼへ
第6章 異化作用としての経験
第7章 子どもが生きられる空間
終章 子どもの自己形成空間
著者等紹介
高橋勝[タカハシマサル]
1946年神奈川県生まれ。1977年東京教育大学大学院教育学研究科博士課程単位取得満期退学。横浜国立大学教育人間科学部教授、教育哲学、教育人間学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
有智 麻耶