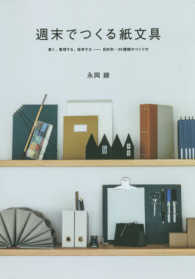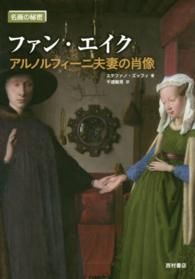出版社内容情報
人間は誤りを犯す存在である。試行錯誤の過程で人は批判的精神と主体性を身につけて成長し、文化も知識も成長する。
生徒は「伝達」による知識の受容者ではなく、能動的、自発的に学ぶ実践者でなければならない。
ポパーの批判的合理主義の思想をバックに、ピアジェ、スキナー、モンテッソーリ、ニイル、ロジャースら20世紀の教育思想を捉え直した本書は、今日の教育改革(「生きる力」「個性重視」などスローガン先行の現状において)に有効な実践的・理論的な指針を与えるであろう。
目次
第1部 隠喩と常識
第1章 教育の三つの隠喩
1 導きとしての教育
2 伝達としての教育
第2章 カール・ポパーの進化論的認識論
1 知識についての常識理論
2 誤りを証明しうる可能性―科学的知識のための新しい水準
3 20世紀の教育理論―誤りからの学習
第2部 いかに誤りから学習するか
第3章 ジャン・ピアジェ
1 認知発達の四段階
2 知識の構造主義理論
3 誤りからの学習
4 誤りの発見―選択能力
5 ピアジェと教育
第4章 B・F・スキナー
1 行動の原因
2 スキナーのダーウィン説
3 教授工学
4 スキナーのラマルク説
5 スキナーの決定論
6 オペラント条件づけ―再解釈
第3部 教師はいかに生徒の誤りからの学習を援助するか
第5章 マリア・モンテッソーリ
1 教育的環境の創造
2 自由な環境
3 応答的環境
4 モンテッソーリ方式の拡大
5 援助的環境
6 モンテッソーリの権威主義
第6章 A・S・ニイル
1 自由な学校
2 応答的環境
3 援助的環境
4 制限
第7章 カール・ロジャーズ
1 来談者中心の療法
2 学習者中心の教育
3 ロジャーズの権威主義
第4部 誤りからの学習
第8章 教育のダーウィン的理論
1 生徒の概念
2 教師の役割
3 教育のダーウィン的理論のさらなる意義
原注
参考文献(抜粋)
訳者あとがき
内容説明
ピアジェ、スキナー、モンテッソーリ、ニイル、ロジャーズら20世紀の進歩的理論を再解釈。「伝達の教育」ではない「誤りから学ぶ」ダーウィン的理論の共通性に注目し、教育理論の更なる進化をもくろむ。
目次
第1部 隠喩と常識(教育の三つの隠喩;カール・ポパーの進化論的認識論)
第2部 いかに誤りから学習するか(ジャン・ピアジェ;B.F.スキナー)
第3部 教師はいかに生徒の誤りからの学習を援助するか(マリア・モンテッソーリ;A.S.ニイル;カール・ロジャーズ)
第4部 誤りからの学習(教育のダーウィン的理論)
著者等紹介
五十嵐敦子[イガラシアツコ]
1954年生まれ。’88年、上智大学大学院文学研究科博士後期課程教育学専攻修了。教育哲学・幼児教育学専攻。実践女子短期大学講師
中山幸夫[ナカヤマユキオ]
1956年生まれ。’84年、上智大学大学院文学研究科後期博士課程教育学専攻修了。教育哲学・教育方法学専攻、敬愛大学助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Kazuki