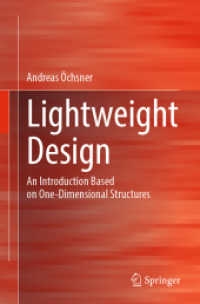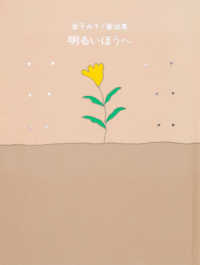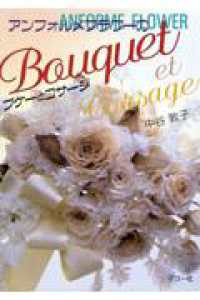出版社内容情報
第二次大戦後、ユネスコによる「国際理解のための教育」が提唱され、国家・国民・文化間の理解・協力・共存をめざす主張や実践が数多く生まれた。さらに70年代以降、アメリカで「グローバル教育」と位置づけられて、平和教育・開発教育などへの広がりをみせている。本書は、こうした動きの中で、イギリスで構想されたワールド・スタディーズに焦点をあて、その教育理念と実践例を明らかにする。国際理解のためのカリキュラム、単元事例(少数民族、ジェンダー、開発問題など)を詳しく紹介、グローバル化した時代にふさわしい教育内容を探る。
【目次】
第Ⅰ部 ワールド・スタディーズとは
第1章 グローバル教育としてのワールド・スタディーズ
1 グローバル教育、ワールド・スタディーズの位置
2 グローバル教育のカリキュラムづくりをめざして
第2章 ワールド・スタディーズの成立と発展
1 成立の背景
2 成立当時のイギリス中等教育における世界に関する学習の状況
3 成立期の活動と成果
4 1980年代以降の変容と発展
第3章 1980年代のワールド・スタディーズの理論
1 世界観
2 目的
3 目標
4 教育観と学習過程
5 単元構成の方法
6 初等教育・幼児教育段階へのワールド・スタディーズの導入
第Ⅱ部 ワールド・スタディーズの単元事例
第4章 ジェンダーに関する問題をとりあげた単元
1 単元の全体的構成
2 小単元の学習過程と学習方法の検討
3 小単元にみられるワールド・スタディーズの特色
第5章 少数民族の問題をとりあげた単元
1 単元「アポリジニーの見方」とその構成
2 小単元の学習過程と学習方法の検討
3 本単元にみられるワールド・スタディーズの特色
第6章 開発問題をとりあげた単元
1 「開発問題」の学習における課題
2 開発教育教材『食糧問題』の構成とその特色
3 ワールド・スタディーズの単元「食べ物こそ第一」の構成とその特色
4 『食糧問題』のにおける「開発問題」のとりあげ方
第7章 中等教育を対象とする教材開発
1 教材の作成過程と全体構成
2 学習過程とその特色
3 中東教育用教材としての『食糧問題』の特色と課題
終章 グローバル教育としてのワールド・スタディーズ
1 ワールド・スタディーズの意義と課題
2 グローバル教育研究への示唆
注
主要参考文献
資料
あとがき
索引
内容説明
開発教育、平和教育など国際理解をめざす教育の内容はどうあるべきなのか。グローバルな理解と自己探究との統合をはかるカリキュラムと単元構成の具体例を詳しく紹介。
目次
第1部 ワールド・スタディーズとは(グローバル教育としてのワールド・スタディーズ;ワールド・スタディーズの成立と発展;1980年代のワールド・スタディーズの理論)
第2部 ワールド・スタディーズの単元事例(ジェンダーに関する問題をとりあげた単元―「ジェンダーにかかわる問題」の場合;少数民族の問題をとりあげた単元―「アボリジニーの見方」の場合;開発問題をとりあげた単元―「食べ物こそ第一」の場合;中等教育を対象とする教材開発―開発教育教材『食料問題』の場合;グローバル教育としてのワールド・スタディーズ)
著者等紹介
木村一子[キムラカズコ]
1953年広島県に生まれる。1976年広島大学教育学部高等学校教員養成課程社会科専攻卒業。広島大学附属福山中・高等学校に社会科教諭として勤務。1989年同退職。1999年名古屋大学大学院教育学研究科博士課程修了。2000年博士(教育学)取得
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。