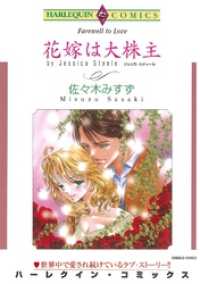出版社内容情報
医の倫理は古代から問われてきたが、1970年代に入ると、生命科学と医療技術の著しい進展によって全く新しい学際的な議論が求められるようになってくる。後に生命倫理とかバイオエシックスと呼ばれるようになる新しい考え方は、ではどのように生まれてきたのだろうか。本書は生命倫理の故郷であるアメリカでの歴史を追う。全体は三部構成である。Ⅰ部は人体実験をめぐる諸問題。Ⅱ部は臓器移植や重度障害児の治療停止の問題など。Ⅲ部は行政側の対応や各種委員会の報告などが扱われる。生命倫理がしだいに形を成し、いくつかの原則にまとめられて
目次
序 関連事項年表
Ⅰ 人体実験をめぐる問題
第1章 「倫理学と臨床研究」と議論の始まり
1 ビーチャーの「倫理学と臨床研究」
2 カッツの回想
3 「ニュルンベルグ綱領」と「ヘルシンキ宣言」
4 科学的な人体実験の登場:ベルナールとボーモント
5 戦時体制下の医学研究:CRM、そしてNIH
6 「倫理学と臨床研究」以後:NIHとFDAの対応
7 最初の哲学者:ハンス・ヨナス
8 ラムジーの『人格としての患者』
9 ヨナス、ラムジーと生命倫理
第2章 社会の変化
1 社会的意識変化:非宗教的多元論的倫理学の希求
2 消費者モデルの導入
3 医療過誤裁判とインフォームド・コンセント
4 インフォームド・コンセントと医療と変化
Ⅱ 何も隠されていない
第1章 シアトル人工腎臓センター、神様委員会
1 「彼らは、誰が生き、誰が死ぬかを決定する」
2 神を演じること
3 誰が神を演じるのか
第2章 臓器移植
1 臓器移植をめぐる専門家の責任
2 心臓移植の登場
3 ハーヴァード大学医学部臨時委員会
第3章 重度障害新生児の治療停止
1 ジョンズ・ホプキンス・ケース
2 解答の個別化、シャウの主張
3 ダフとキャンベルの報告
4 インジルフィンガー、ベッドサイド・エシックスからの批判
5 誰が決定すべきか
6 カリフォルニア大学の試み
Ⅲ 国家委員会と生命倫理の成立
第1章 国家研究法の歩み
1 ケネディ研究所とヘイスティングス・センター
2 モンデール公聴会
3 胎児研究とケネディ公聴会
4 タスキギー事件
第2章 国家委員会と「倫理学の新しいやり方」
1 被験者保護のための国家委員会
2 『報告と勧告、胎児に対する研究』
3 「新しい倫理学のやり方」
第3章 『ベルモント・レポート』と原則主義
1 『ベルモント・レポート』の成立
2 三つの原則と三つの応用
3 『ベルモント・レポート』における原則の位置
第4章 『生命医学倫理の諸原則』と原則主義の意味
1 『生命医学倫理の諸原則』:応用倫理としての生命倫理
2 倫理学理論と原則
3 『生命医学倫理の諸原則』への批判
4 原則主義と生命倫理の成立
註
あとがき
文献表
人名索引/事項索引
内容説明
生命科学や医療技術の飛躍的進展に伴う、新しい問題群に対応する新しい倫理。医療にどのように関わるべきか。
目次
1 人体実験をめぐる問題(「倫理学と臨床研究」と議論の始り;社会の変化)
2 何も隠されていない(シアトル人工腎臓センター、神様委員会;臓器移植;重度障害新生児の治療停止)
3 国家委員会と生命倫理の成立(国家研究法への歩み;国家委員会と「倫理学の新しいやり方」;『ベルモント・レポート』と原則主義;『生命医学倫理の諸原則』と原則主義の意味)