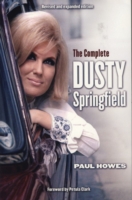出版社内容情報
ハイデガーを咀嚼し,多彩なテキストを通して,存在の〈異他性〉に迫る。澄明な文章が織りなす哲学の始源の問い。
目次
序章 うつつの夢
Ⅰ 生きられた現実、あるいは夜
1 森は逃げていく
2 生きられた瞬間の闇
3 夜の目覚め
Ⅱ 言語と非言語
1 騙された世界
2 非言語の要請
3 非言語の非場所
Ⅲ 滅びのなかの生成
1 存在:無:同一
2 存在刹那
3 反転の論理
Ⅳ クワシ・ウルマチ
1 死の存在論
2 隠しの技法
3 ハパックスの論理
Ⅵ 無人論―わたしはすでに<外>で遊んでいる―
1 世界劇場
2 内在の超越
3 最後の舞台
終章 他界からの視線
1 帰還するまなざし
2 仮死光線の演劇
3 浄土の錬金術
あとがき
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さえきかずひこ
14
筆者の思索はハイデガーが『存在と時間』の存在論で提出した本来性と非本来性の間を往き来する。文体は博覧を感じさせるが平易であり、わが国の精神史(能の他界性や一遍の踊り念仏の脱自性)をハイデガーのそれと交錯させ、類比的に見ていく傾向にある。真摯なハイデガー研究の徒たちからは、彼の手つきについて批判が生じるような気もするが、一般読者においてはハイデガーの実存を日本的に解釈することでより深い理解を促そうと努める点が有用と見なされるのではないだろうか。前期ハイデガーと現象学、そして東洋哲学に関心のある向きには良書。2019/01/05
バナナフィッシュ。
5
多い注解が役立った。「序章」で述べているが、至極簡単、簡素なことを何度も言い換えながら説明していくので、得られるものはそれほど多くはないかもしれない。しかし、ハイデガーを中心にレヴィナス、フッサール、メルロ=ポンティなどの現象学の哲学者達、および関連する俳人、小説家、劇作家等々、この著書の視線が向けられている範囲は広く、興味は尽きそうにない。2015/01/18
じょに
5
ハイデガーの講義録も参照して、ハイデガーの哲学を読み解いていこうという試み。一言でまとめるなら、無常の哲学とでも言うのか。演技論や能についての考察が面白い。内在故の超越。こういう「神秘主義的」とみなされそうな話も嫌いじゃない。どうでもいいけど、現代思想のタームに繋げて行って、それハイデガーも言ってるし的な感じに仕上がってるあたりがニクい(笑)2009/02/02
-
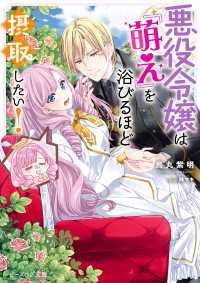
- 電子書籍
- 悪役令嬢は『萌え』を浴びるほど摂取した…