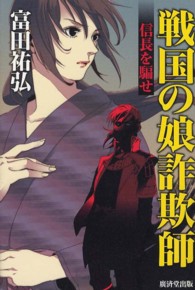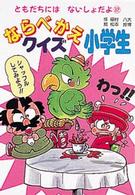出版社内容情報
プラトンの遺産を受け継ぎ、聖書において新しい探求の場を拓いたユスティノス。ヘレニズム・ローマ期の時代思潮に抗して立つ哲学者の姿を鮮やかに切り出す。
教父哲学と呼ばれる学問分野が次第に輪郭を見せ始めている。アウグスティヌスが中心であったが、ここ30年の間に他の教父やグノーシス主義の研究も急速に進んだ。本書は2世紀の代表的な教父であるユスティノスの、これまで研究が手薄であった側面に着目、現存する三著作の読解を通して全体知を憧憬する哲学者の思索を追体験する。
関連書:同著者 『グノーシスと古代宇宙論』
序章 教父ユスティノスの生涯、そして思索の足跡
1 生涯と著作
2 現存三著作の整合性
第一章 二世界論の超克──見えるもの、見えぬもの
1 回心における哲学
2 二世界論からキリスト教形而上学へ
3 イデア論の継承
第二章 預言者の哲学──言葉と行為
1 青銅の蛇の物語──予型論の意義をめぐって
2 「語りえぬ者」について
第三章 受肉の哲学──全体知と部分知
1 「ソクラテスはキリスト教徒であった」という言葉の二面性
2 ロゴスとデュナミス──受肉論に寄せて
結び
文献表
人名索引/事項索引/詳細目次
内容説明
プラトンの遺産を受け継ぎ、聖書において新しい探求の場を拓いたユスティノス。ヘレニズム・ローマ期の時代思潮に抗して立つ哲学者の姿を鮮やかに切り出す。
目次
序章 教父ユスティノスの生涯、そして思索の足跡(生涯と著作;現存三著作の整合性)
第1章 二世界論の超克―見えるもの、見えぬもの(回心における哲学;二世界論からキリスト教形而上学へ;イデア教の継承)
第2章 預言者の哲学―言葉と行為(青銅の蛇の物語―予型論の意義をめぐって;「語りえぬ者」について)
第3章 受肉の哲学―全体知と部分知(「ソクラテスはキリスト教徒であった」という言葉の二面性;ロゴスとデュナミス―受肉論に寄せて)
著者等紹介
柴田有[シバタユウ]
1942年東京都に生まれる。1974‐80年東京大学大学院人文科学研究科(西洋古典学)(博士課程単位取得満期退学)。1975‐78年ストラスブール大学大学院人文科学研究科に留学(宗教学博士号)。専攻は教父哲学、ヘレニズム思想。明治学院大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。