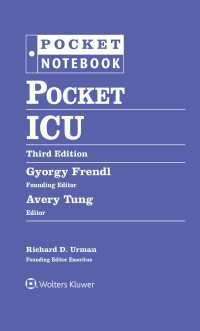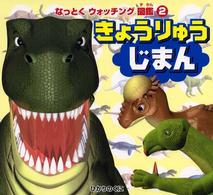出版社内容情報
●内容
本書では,私たちの脳がいかに学び,いかに考え,そしていかにして,私たちはそういったことのできるマシンを作れるのか,という問いに対して,「知の探検」を試みています。
今日まで,専門的で難しい問題の解決を手助けするプログラムが組み込まれたコンピュータは多数開発されてきました。ところが,私たちの日常生活を助けてくれるような,「常識的な思考」ができるマシンはいまだに存在しません。なぜ,そのようなマシンの実現が難しいのでしょうか? 普通の人々が持っている常識を持ち,臨機応変なことのできるマシンを,なぜ実現できないのでしょうか?
1950年代に,"人工知能"と呼ばれる研究分野は,いくつかの困難な技術的問題を解決するコンピュータ・プログラムを開発し,成功裡にスタートしました。もしマシンがいくつかの難しい問題を解決することができれば,それよりやさしい多くの問題も解決できると誰もが信じました。しかしながら,これは間違いに終わりました。
これまで人間の常識的な思考についての研究は盛んではありませんでした。なぜならば,大部分の研究者は物理学者のまねをしようとしたからです。つまり,考えることのできるマシンの実現に向けて,ある一つの"統一理論"を作ろうとしてきたからです。
これに対して本書では,これまでとは違うアプローチを提案しています。従来のどの理論が'正しい'かを見つけようとするのではなく,もっと大きな構造にそれらを組み込むことによって,すべての理論の長所を結びつけようとしています。本書のどの章も,思考システムが行き詰まるのを防ぐために数種類の方法を示し,さまざまな状況に応じて,多くの"思考路"の中のいずれかにスイッチを切り替え対処できるように構成しました。
本書を長時間「探検」することによって,読者に多くの役に立つ新しい"思考路"を提供しています。
目次
第1章 恋をする
第2章 愛着と目標
第3章 痛みから苦痛まで
第4章 意識
第5章 心的活動の階層
第6章 常識
第7章 思考
第8章 思考の豊かさ
第9章 自己
著者等紹介
ミンスキー,マーヴィン[ミンスキー,マーヴィン][Minsky,Marvin]
マサチューセッツ工科大学(MIT)メディア・アート&サイエンスの東芝プロフェッサーであり、電子工学およびコンピュータ科学の教授。コンピュータ・グラフィックス、知識と意味論、マシン・ビジョン、およびマシン・ラーニングの分野に多大な貢献をし、宇宙探索に関する技術にも情熱を注いだ。1990年日本国際賞を受賞。触覚センサー、視覚スキャナーと、ソフトウェアおよびインタフェースを用いてロボットハンドを開発し、1951年世界初のニューラル・ネットワーク学習マシンを開発
竹林洋一[タケバヤシヨウイチ]
1974年慶應義塾大学工学部卒業。1980年東北大学大学院工学研究科博士課程修了。工学博士。1981年東芝総合研究所研究員。1985年マサチューセッツ工科大学メディア研究所客員研究員。2000年東芝研究開発センター知識メディアラボラトリー技監。2002年静岡大学情報学部教授。2003年デジタルセンセーション株式会社会長兼務。2006年静岡大学創造科学技術大学院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
エジー@中小企業診断士
nchiba
egu
あんみつの人