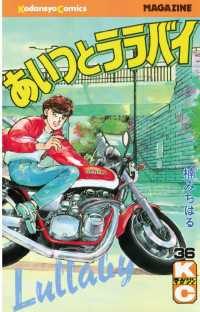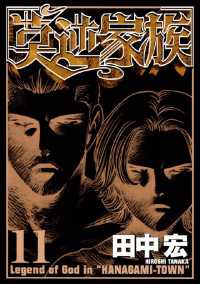出版社内容情報
●内容
本書はStuart RussellおよびPeter Norvigによる Artifcial Intelligence - A Modern Approach (Second Edition) の翻訳である。この第2版の出版は2003年であり,第1版の出版から8年を経過している。その間に,人工知能の研究も大幅に進展し,その結果,本改訂版はほぼ全編に及ぶ大幅なもので,新たな章の追加を始めとして,おそらく全書の半分くらいにまで及んでいる。
本書の翻訳出版は,第1版に引き続き,共立出版(株)にお引き受けいただいた。翻訳者については,これも第1版の場合と同様,章単位で選定することとした。本書の大幅な改訂に伴い,翻訳者の追加変更を行った。幸い,本書の優れた内容についての御理解をいただいて,各翻訳者には快く翻訳作業を引き受けていただいた。さらに,翻訳者の中から数名の方々にお集まりいただき,翻訳についての方針を取り決めた。第1版と同様,原著のLATEXファイルを利用することとし,翻訳の品質の維持に注意を払ったことは,もちろんである。
大部分の訳語については第1版を継承したが,いくつかの訳語では,一昨年に共立出版から刊行された『人工知能学事典』を参考にした。
本書は,原著者の前書きにもあるように,人工知能の主要な分野を網羅している。また,従来の教科書とは異なり,多くの最新の話題も含んでいる。そして,本書の表紙を飾る帯に"The Intelligent Agent Book"とあるように,全体が「エージェント」の観点から書かれている。そのため,記述全体に統一性が保たれ,異なった分野間の関連性も明らかになっている。本書は,全体を通じて,例を多く用いたわかりやすい記述になっていると同時に,背後にある理論を原理から丁寧に解説しているので,人工知能についての深い理解が可能である。
本書のタイトルの原文は,"Artifcial Intelligence - A Modern Approach" であるが,翻訳にあたり,表紙の帯のタイトルを借用して,タイトルを『エージェントアプローチ人工知能』とした。もともとの副題である"A Modern Approach"の意味するところは,原著者の前書きに見られるように,「人工知能の各部分領域をそれらの独自の歴史的文脈に沿って解説するのではなく,現在知られている事柄を共通の枠組みの中で再構築することを試みた」ということを反映している。すなわち,人工知能という膨大な分野を統一的な視点で捉えなおした力作である。そのため,本書は世界中から絶大は評価を得ていると聞いている。
以下は,本書の第1版に対する監訳者である筆者の前書きからの抜粋である。
「人工知能の研究が実世界の問題に対して期待されたほどの成果をあげえなかったことから,産業界から評価されない時期がしばらく続いたが,本書は,プランニングや機械学習などの記述に見られるように,その低い評価を見直すきっかけを与えるのに十分な内容を含んでいることも見逃せない。もちろん,人工知能の研究は日進月歩を遂げているので,とくに最先端の分野では既にその内容が古くなっているところも見受けられるが,人工知能全体を見渡すには恰好な入門書である。ここしばらくは,本書を凌ぐ人工知能の教科書は出現しないのではなかろうか。」 この記述は,さらに強化された形で,そのまま第2版の監訳者前書きにも該当すると思われる。以下に原著者自身の第2版の前書きからも引用しよう。
「1995年当時に比べて,AIの果実は比較にならないほど実用技術として成熟してきたことを知らしめたい。たとえば,第1版でのプランニングアルゴリズムは高々数十ステップのプランしか生成できなかったが,本版でのアルゴリズムは数万ステップへと桁違いの性能を示している。同様の桁単位の改善は,確率推論,自然言語処理などの分野でも見られる。」
人工知能分野でのこのような発展が本改訂版に反映されているのは当然である。
(監訳者前書きより抜粋)
【目次】
I部 人工知能
1 序論
1.1 AIとは?
1.2 人工知能の基礎
1.3 人工知能の歴史
1.4 最新技術
1.5 まとめ
2 知的エージェント
2.1 エージェントと環境
2.2 良い振舞い:合理性の概念
2.3 環境の性質
2.4 エージェントの構造
2.5 まとめ
II部 問題解決
3 探索による問題解決
3.1 問題解決エージェント
3.2 例題
3.3 解の探索
3.4 情報のない探索戦略
3.5 繰返し状態の回避
3.6 部分的知識をもつ探索
3.7 まとめ
4 知識に基づく探索と探査
4.1 知識に基づく(ヒューリスティック)探索手法
4.2 ヒューリスティック関数
4.3 局所探索アルゴリズムと最適化問題
4.4 連続空間における局所探索
4.5 オンライン探索エージェントと未知環境
4.6 まとめ
5 制約充足問題
5.1 制約充足問題
5.2 制約充足問題のための後戻り探索
5.3 制約充足問題のための局所探索
5.4 問題の構造
5.5 まとめ
6 敵対探索
6.1 ゲーム
6.2 ゲームにおける最適解
6.3 アルファ‐ベータ枝刈り
6.4 不完全リアルタイム決定
6.5 偶然の要素を含むゲーム
6.6 ゲームプログラムの現在
6.7 考察
6.8 まとめ
III部 知識と推論
7 論理的エージェント
7.1 知識エージェント
7.2 Wumpus World
7.3 理論
7.4 命題論理:とても単純な理論
7.5 命題論理における推論パターン
7.6 実用的な命題推論法
7.7 命題論理エージェント
7.8 まとめ
8 一階述語論理
8.1 再び表現について
8.2 一階述語論理の統語論と意味論
8.3 一階述語論理の利用
8.4 一階述語論理における知識工学
8.5 まとめ
9 一階述語論理による推論
9.1 命題論理 対 一階述語論理
9.2 単一化ともちあげ
9.3 前向き連鎖
9.4 後向き連鎖
9.5 融合法
9.6 まとめ
10 知識表現
10.1 オントロジ工学
10.2 カテゴリとオブジェクト
10.3 行為,状況,イベント
10.4 心的事象と心的オブジェクト
10.5 インターネットショッピングの世界
10.6 カテゴリのための推論システム
10.7 デフォルト情報をを使った推論
10.8 真理維持システム
10.9 まとめ
IV部 プランニング
11 プランニング
11.1 プランニング問題
11.2 状態空間探索によるプランニング
11.3 半順序プランニング
11.4 プランニンググラフ
11.5 命題論理を用いたプランニング
11.6 プランニングのアプローチの解析
11.7 まとめ
12 実世界におけるプランニングと行為
12.1 時間,スケジュール,資源
12.2 階層的タスクネットワークプランニング
12.3 非決定的領域におけるプランニングと行為
12.4 条件付プランニング
12.5 実行モニタリングと再プランニング
12.6 連続プランニング
12.7 マルチエージェントプランニング
12.8 まとめ
V部 不確実な知識と推論
13 不確実性
13.1 不確実性のもとでの行為
13.2 確率の基本的な記法
13.3 確率論の公理
13.4 完全結合分布を用いた推論
13.5 独立
13.6 ベイズ規則とその使用法
13.7 Wumpus World再考
13.8 まとめ
14 確率推論
14.1 不確実な領域における知識表現
14.2 ベイジアンネットの意味論
14.3 条件付き確率分布の効率的な表現
14.4 ベイジアンネットの厳密推論
14.5 ベイジアンネットの近似推論
14.6 一階論理表現への確率の拡張
14.7 不確実性推論に対するその他のアプローチ
14.8 まとめ
15 時間を伴う確率的推論
15.1 時間と不確実性
15.2 時制モデルの推論
15.3 隠れマフコフモデル
15.4 カルマンフィルタ
15.5 動的ベイジアンネット
15.6 音声認識
15.7 まとめ
16 単純な意思決定
16.1 不確かさのもとでの信念と願望の結び付け
16.2 効用理論の基礎
16.3 効用関数
16.4 多属性効用関数
16.5 意思決定ネットワーク
16.6 情報の価値
16.7 意思決定理論的エキスパート・システム
16.8 まとめ
17 複雑な意思決定
17.1 逐次意思決定問題
17.2 価値反復
17.3 方策反復
17.4 部分観測マフコフ意思決定過程
17.5 意思決定論的エージェント
17.6 複数のエージェントにおける決定:ゲーム理論
17.7 機構設計
17.8 まとめ
VI部 学習
18 経験からの学習
18.1 学習の形式
18.2 帰納学習
18.3 決定木の学習
18.4 アンサンブル学習
18.5 学習はなぜ可能か:計算論的学習理論
18.6 まとめ
19 学習における知識
19.1 学習の論理的な定式化
19.2 学習における知識
19.3 説明に基づく学習
19.4 関連情報を用いた学習
19.5 帰納論理プログラミング
19.6 まとめ
20 統計的学習手法
20.1 統計的学習
20.2 完全なデータからの学習
20.3 隠れ変数を含む学習:EMアルゴリズム
20.4 事例ベース学習
20.5 ニューラルネットワーク
20.6 カーネルマシン
20.7 応用事例:手書き数字認識
20.8 まとめ
21 強化学習
21.1 はじめに
21.2 受動強化学習
21.3 能動強化学習
21.4 強化学習における一般化
21.5 制作の探索
21.6 まとめ
VII部 コミュニケーション,知覚,行動
22 コミュニケーション
22.1 行為としてのコミュニケーション
22.2 英語の断片のための形式文法
22.3 統語解析(構文解析)
22.4 拡張文法
22.5 意味解釈
22.6 多義性と多義性解消
22.7 談話理解
22.8 文法帰納
22.9 まとめ
23 確率的言語処理
23.1 確率言語モデル
23.2 情報検索
23.3 情報抽出
23.4 機械翻訳
23.5 まとめ
24 知覚
24.1 序論
24.2 画像の生成
24.3 初期画像処理演算
24.4 視覚を用いた3次元情報の抽出
24.5 対象の認識
24.6 対象の操作とナビゲーションのための視覚の利用
24.7 まとめ
25 ロボティクス
25.1 はじめに
25.2 ロボットハードウェア
25.3 ロボットの知覚
25.4 動作計画
25.5 不確かな運動の計画
25.6 運動すること
25.7 ロボットのソフトウェアアーキテクチャ
25.8 応用領域
25.9 まとめ
26 哲学的基礎
26.1 弱いAI: 機械は知的に振舞うことができるか?
26.2 強いAI:機械は本当に考えることができるか?
26.3 AIの発展に関する倫理と危険性
26.4 まとめ
27 AI:現在と未来
27.1 エージェントの諸構成素
27.2 エージェントアーキテクチャ
27.3 我々は正しい方向に進んでいるか?
27.4 もしAIが本当に成功したらどうなるか?
付録A 数学の諸概念について
A.1 計算量の解析とO ( )表記
A.2 ベクトル,行列,線形代数
A.3 確率と分布
付録B 言語とアルゴリズムについての注意
B.1 形式言語のバッカス‐ナウア記法(BNF記法)による定義
B.2 アルゴリズムの擬似コードによる記述
B.3 オンライン・ヘルプ
目次
1 人工知能
2 問題解決
3 知識と推論
4 プランニング
5 不確実な知識と推論
6 学習
7 コミュニケーション、知覚・行動
著者等紹介
ラッセル,スチュワート[ラッセル,スチュワート][Russell,Stuart J.]
オックスフォード大学物理学科を主席で卒業し、スタンフォード大学から計算機科学の博士号を取得。その後、カリフォルニア大学バークレイ校のファカルティメンバとなり、現在は教授、インテリジェントシステムセンター長かつSmith‐Zadeh工学部学部長。1990年に、人工知能研究の功績により、NSF Presidential Young Investigator Awardを受賞。1995年、人工知能分野の最高の国際賞であるComputer and Thought Awardを受賞。米国人工知能学会のフェローであり、前理事
ノーヴィグ,ピーター[ノーヴィグ,ピーター][Norvig,Peter]
ブラウン大学で応用数学の学士号を取得し、カリフォルニア大学バークレイ校で博士号を取得。南カリフォルニア大学教授、バークレイ校での研究ファカルティメンバ、サンマイクロシステムズ研究所の幹部研究員、Junglee社の上級科学者、NASA Ames Research Centerのコンピュータサイエンス部長を経て、現在Googleの検索品質部長。また米国人工知能学会のフェローであり、前理事
古川康一[フルカワコウイチ]
1965年東京大学工学部計数工学科卒業。1967年同大学院工学系研究科修士課程修了。同年、通産省工業技術院電気試験所入所。1982年(財)新世代コンピュータ技術開発機構へ出向。1992年慶應義塾大学環境情報学部教授。1994年同大学院政策・メディア研究科教授。2008年退職、現慶應義塾大学名誉教授、工学博士。この間、論理プログラミング、機械学習、帰納論理プログラミング、スキルサイエンスなどの研究に従事。日本ソフトウエア科学会、情報処理学会、日本人工知能学会、日本認知科学会、バイオメカニズム学会、各会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。