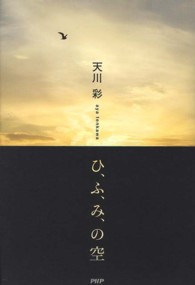出版社内容情報
シオランは,1937年に祖国ルーマニアをあとにした。本書は,その年に書かれた記念すべき著作である。パリに移ってからフランス語で書いたものにはない痛切な抒情のトーンで,彼は,若き日の感情の激発を綴る。ここには,バルカンの若き一知識人の破調の言葉が刻みこまれている。そしてそこにみなぎるのは,まぎれもなくルーマニア精神そのものにほかならない。
内容説明
E.M.シオラン―パリのアパルトマンの一室から、生に対する呪詛を発しつづける異端の思想家。彼は、1937年に祖国ルーマニアをあとにした。本書はその年に書かれた記念すべき著作である。パリに移ってからフランス語で書かれたものにはない、若々しく痛切な抒情のトーンで彼は綴る―「私たちを聖者たちに近づけるものは認識ではない、それは私たち自身の最深部に睡っている涙の目覚めである」。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
13
痛切で哀しい本だ。そして、触れれば流血しそうなほど苛烈な本でもある。人はその苦悩の深み、最奥の涙によってのみ、神と共にある聖者に近づくことができる。だが、聖者でも重罪人でもない凡庸さを自覚したシオランには、どんなに苦悩を突き詰めても聖者たちとそれ以上歩めない一線がある。それを知っているからか、神聖性に対する闘争の炎も本書には燃え上がる。これは苦悶に満ちた生から叫んだ聖性への最大の賛辞であり、また憤りに満ちた宣戦布告なのだ。哀しみの形而上詩がここにはある2012/09/16
nina
5
この本が出版された1937年、シオランは生まれ故郷のルーマニアから芸術の都パリに移り住んでいる。その頃、大戦前夜のパリといえばシュルレアリストの連中やら世界中から集まった有名無名のアーティストと有象無象がカフェを占拠して夜な夜な群れ集っていたと想像されるが、その中でこのシオランの悲しみと皮肉とある種の熱情に溢れたアフォリズムがどのように受け入れられたのか。神、聖者、涙、音楽、エクスタシー…その絶望を、虚無を、孤独を愛するがゆえに孤高の魂をのせたかの漂流船は永遠に思念の海を彷徨い続けるように思える。2013/08/08
3247
3
「私たちを聖者に近づけるものは認識ではない、それは私たち自身の最深部に睡っている涙の目覚めである。そのときはじめて、私たちは涙を通して認識に達するのであり、そして人がひとりの人間であったあとでいかにして聖者になりうるかを理解するのである」 「「楽園」は意識の底で嘆き悲しみ、記憶が一方で涙を流している。こうして私たちは涙の形而上学的意味に、悔恨の展開としての生に思いをいたすのである」2015/06/05
いなお
2
記憶は時間への反証にとどまらない。それはまたこの世界への反逆でもあり、私たちの内部に、ありえたかも知れぬ過去のさまざまの世界と、楽園をもって飾られるそれらの世界の頂点とをぼんやりと啓示するのである。2017/04/14
さへど
0
二番目に読んだシオランの本。「絶望のきわみで」を読了してすぐに読んだのだが、この本の頭の方では聖者、聖女、キリスト教…と聖性のテーマが色濃く、絶望を雄弁に語ったシオランらしくないとその部分では感じた。しかし読み進めるとシオランらしい厭世観が見え始め、キリスト教や神への皮肉が多彩な表現で語られなんとも痛快だった。読了後には聖性という1つのテーマに絞ったシオラン観がたっぷり読めたことで満足感があった。